帳票を紙で記録すると、ファイリングの手間がかかり管理が煩雑になってしまいます。そこで、昨今は帳票を電子化してデータ保管する方法が一般的です。
実際に、電子帳簿保存法では、2024年1月から電子取引のデータ保存を義務付ける内容が盛り込まれており、対策が必要です。
しかし「帳票を電子化する方法やメリットがわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、帳票を電子化するメリットや移行手順を中心にご紹介します。
- 帳票の電子化によるメリットを知りたい
- 電子帳簿保存法に合わせて帳票を電子化させたいので、紙からの移行方法を知りたい
- 電子帳票を簡単に保管できるツールがあれば知りたい
という方はこの記事を参考にすると、帳票を電子化する具体的なメリットや移行手順だけでなく、帳票管理の手間を解消する方法も分かります。
目次
帳票とは
帳票とは、「企業や個人事業主がお金やモノのやりとりをした際に作成する書類のこと」を指します。
具体的には、会社の経営状況を確認する文書の「帳簿」と、日々の取引やお金のやり取りごとに作成する文書「伝票」を合わせた総称です。
帳票は企業のお金やモノの流れを把握し、企業活動の状況を確認するために用いられる重要な書類と言えます。
帳票を電子化するメリットとは
ここでは、帳票を電子化するメリットを紹介します。紙から電子媒体での管理に移行すると、以下の効果が得られて管理の負担を最小限にできるのです。
管理の煩雑さを解消
帳票を電子化すると、管理の煩雑さが解消されます。
紙の帳票は紛失が発生しないように、種別や作成時期に合わせて適切に分類しなければなりません。しかし、帳票類は数年単位での保管が必要になるので、保管年数を重ねるほど過去の資料が見つけにくくなってしまうのです。
そこで、帳票を電子化し検索やフォルダ分けを活用すれば、いつでも必要な情報がすぐに見つけられる体制が整えられます。
消耗品費の削減
帳票の電子化は、消耗品費の削減にも効果的です。
帳票にはさまざまな種別があり、なかには専用の用紙が必要なケースもあります。たとえば、伝票や納品書などを社内で印刷する場合は、ミシン目やファイリング用の穴がある用紙が役立つ一方、利用には専用の用紙を購入する費用が発生します。
さらに、印刷インクや手書きする際に使う文房具といった備品費も併せて必要になり、紙での帳票管理は諸経費がかかるのです。しかし、電子化すると料金コストを抑えられるので、社内の無駄な費用の削減につながります。
勤務場所を問わず帳票が管理可能
勤務場所に関係なく、帳票を管理できる環境を作るには、帳票の電子化が有効です。
昨今では、テレワークを導入する企業が増えています。しかし、紙で帳票を保管していると、オフィス以外での勤務を認めている場合でも、管理のために社員が出社し、対応する手間が発生してしまうのです。
以上のように、特定の業務だけを目的に出社を求めるのは非効率です。したがって、勤務地の影響なく帳票を閲覧・整理するには、電子化を進めることが最適な方法だと言えます。
帳票の電子化に関連する「電子帳簿保存法」とは?
帳票の電子化において「電子帳簿保存法」は重要な関連性があります。
まず、電子帳簿保存法とは「記録や保存における一定の要件を満たすことで、国税に関する帳簿書類の電子管理を認める」と定めた制度です。電子帳簿保存法では、改正により「電子取引を行った場合、取引情報についての記録を一定の要件に沿って電磁的に保存しなければならない」としています。
「取引情報」は取引で受領する見積書や注文書、契約書などの書類に記載される事項を指します。したがって、たとえばインターネットや電子メールで注文書をやりとりした場合、電子帳簿保存法で定められた要件に合わせて電子記録を残す必要があるのです。
以上のことから、企業には帳票類を電子保存できる体制の整備が求められます。
帳票を電子化する進め方
電子に移行する際は、単に紙の帳票をデータ化するだけでなく、社内周知も実施することが重要です。そこで以下では、帳票を電子化する進め方を説明します。
STEP1.社内の帳票類を整理する
まずは、社内に保管されている帳票類を整理します。
帳票は会計関係の書類だけでなく、経営に関わるすべての書類が該当します。そのため、現在社内に保管されている帳票の種別や量を確認し、電子化に備えましょう。
また、帳票が多く移行が難しい場合は、データ化する種別や年度を整理の段階で限定するのもひとつの方法です。
STEP2.電子化について社内周知する
次に、帳票の電子化について社内に周知します。
帳票が電子化されると、従来の紙での管理から業務フローを変更する必要があります。したがって、データ化を始める前に関係する社員に対して、帳票の電子化に至った背景や今後の対応の流れについて事前周知しましょう。
また、帳票の電子化は取引先にも大きな影響を与えます。契約書や見積書などの取引先とのやりとりに関する帳票も電子化する場合、とくに顧客と関わりのあるメンバーには詳細に説明し、顧客への連絡やフォローについて必ずすり合わせておきましょう。
STEP3.帳票を電子化するツールを選ぶ
社内の周知が完了したら、帳票を電子化するツールを選びます。帳票を電子化する方法はさまざまあり、主に以下の手段が挙げられます。
- スキャナーで紙の帳票をPDF化
- Excelを活用してファイルを作成・管理
- 帳票の作成・管理が可能なITツールを導入
紙の帳票をPDF化する方法です。既存の書類をデータ化しやすい方法な一方、スキャンしたデータの修正は困難な点に注意が必要です。
Excelで帳票を作成し、ファイル管理する方法です。Excelを使えば自動計算や表の作成において利便性が高い一方で、保管するファイルが増えるとファイル管理が煩雑になるため、データの保存先を明確化することが重要です。
帳票の作成や管理に対応しているITツールを導入すると、ツール内に情報が集約されるうえ、閲覧や編集が円滑になります。ただし、利用方法が複雑なツールだとメンバーが使いこなせない恐れがあるので、とくに非IT企業は難易度の低いシンプルな機能のツールを選びましょう。
以上のように、PDFやExcelファイルでの管理は、格納場所が決まっていなければ情報が分散するリスクが高まります。したがって、ストレスの発生しない、かつ帳票の作成・管理が可能なITツールが、最も電子帳票を管理しやすい方法だと言えます。
STEP4.帳票の内容を電子化する
最後に、帳票の内容を電子化します。
帳票は先に決めたツールで電子化を進めます。従来紙で管理していた企業は、電子への切り替え業務に時間を要する恐れがあるので、業務に支障が出ないように実行のタイミングは事前に社内調整しましょう。
以上の流れで帳票の電子化が完了します。
【必見】電子帳票の管理が円滑化するおすすめツール
以下では、電子帳票の管理が円滑化するおすすめツールを紹介します。
帳票は経営に関わるあらゆる書類が該当するので、帳票を取り扱う社内メンバーも多岐にわたります。そのため、誰もが電子化した帳票を正しく管理するには「簡単に管理できる環境を構築する」ことが大切です。
そこで、操作が簡単な「情報管理ツール」を導入しましょう。とくに、非IT企業が帳票の電子化を進める際は、ITに不慣れなメンバーでも確実に運用できるツールでなければ、業務が停滞する恐れがあるのです。
結論、電子化した帳票の管理には非IT企業の65歳以上のメンバーでもマニュアルなしで利用できるほど簡単な情報管理ツール「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」は文字だけでなく、ファイル添付にも対応しているうえに「フォルダ」で電子化した帳票を種別ごとに分類可能です。また、ノートを起点に「メッセージ」「タスク」のやりとりが可能で、何の帳票に関する連絡か確認しやすいのです。
電子化した社内の帳票が最も簡単に管理できるツール「Stock」
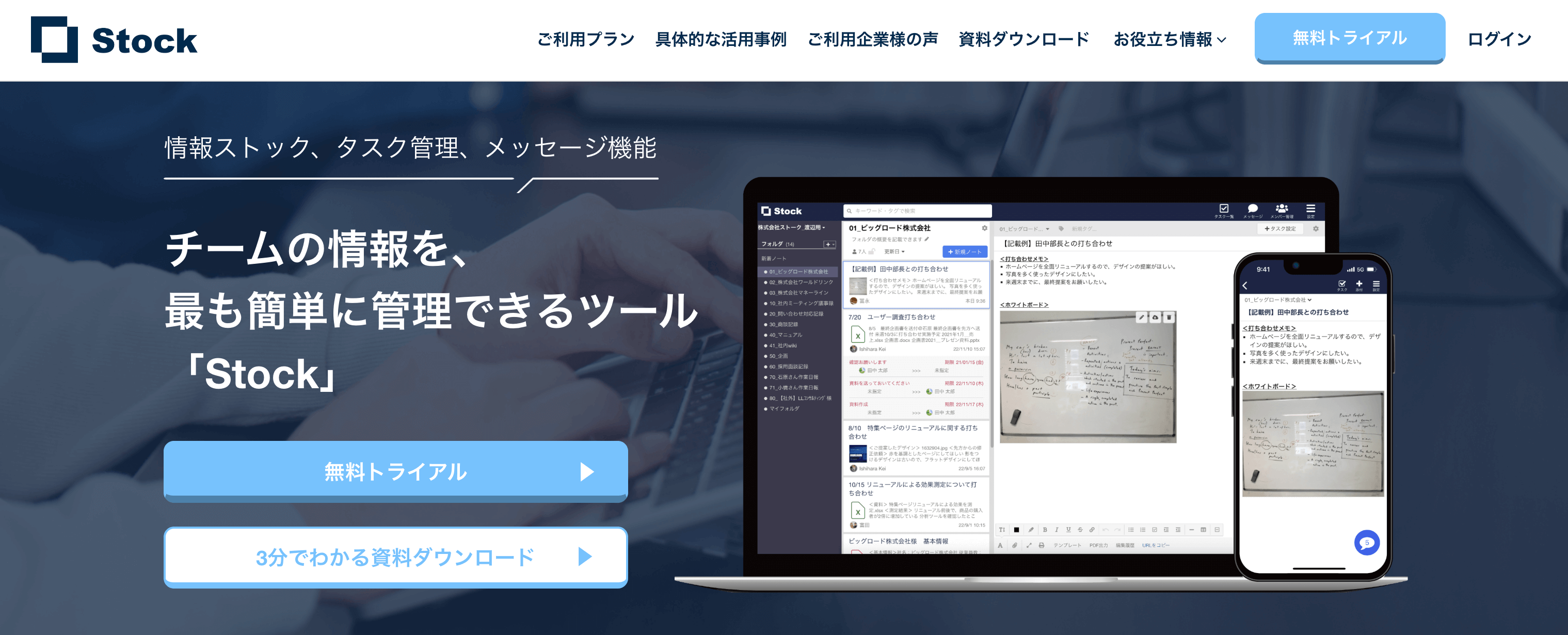
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
※最低ご利用人数:5ユーザーから
帳簿の電子化に関するよくある質問
以下では、帳簿の電子化に関するよくある質問について解説します。電子化についての疑問点を解消したい方は必見です。
帳票の電子化は義務ですか?
帳票の電子化自体は義務ではなく、紙で保存しても問題ありません。
ただし、電子帳簿保存法では「電子取引を行った場合、取引情報についての記録を一定の要件に沿って電磁的に保存しなければならない」と定められています。
そのため、たとえば電子で請求書や見積書をやりとりした場合、適切なシステムを導入するなどして、電子データを安全に保存・管理する必要があります。
電子帳票保存法はいつから義務化されますか?
電子帳簿保存法における電子取引についての電子データ保存は、2024年1月1日から、義務化が開始しています。
ただし、要件を満たす場合には猶予措置が認められる場合もあるため、詳細を確認したうえで対応しましょう。
帳票を電子化するメリットや移行手順まとめ
これまで、帳票を電子化するメリットや移行手順を中心にご紹介しました。
帳票を電子化すれば管理の煩雑さを解消できるうえ、勤務場所を問わず帳票を管理する体制が整えられます。そこで、電子帳票の管理が可能なITツールを活用すれば、簡単に電子化を進められます。
ただし、操作が複雑なITツールの場合、社内に浸透せず、結局紙に戻ってしまう恐れがあります。また、多機能な帳票管理ツールはコストがかかりやすく、手軽に導入できないというデメリットもあるのです。
結論、IT知識に関係なく直感的に操作可能な情報共有ツールの「Stock」一択です。また、500円/ユーザー/月〜利用できるため、運用の負担を最小限に抑えられるのです。
ぜひ「Stock」を導入し、電子化した帳票をストレスなく管理しましょう。
関連記事: 社内向け依頼書の書き方とは?ポイントや例文も紹介




