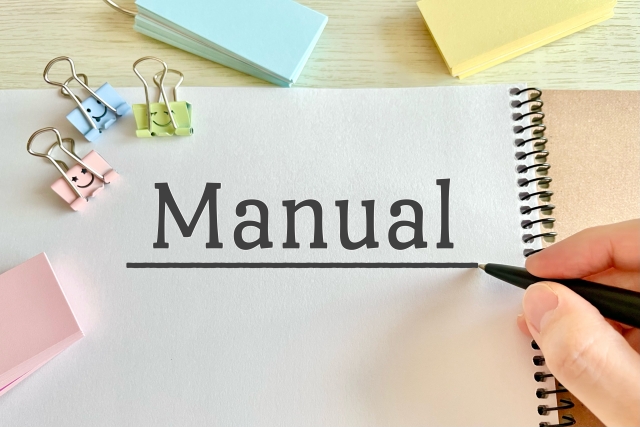建設業において、マニュアルは作業の進め方を統一したり、事故を防いだりするうえで欠かせません。また、マニュアルを効率よく作成するには、記載や修正に時間がかかる紙ではなく「ITツール」を使うのが効果的です。
しかし、なかには「マニュアルの正しい作成方法や、自社に最適なツールが分からない」と悩む建設業界の方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、建設業におけるマニュアルの意義や作成手順、おすすめのツールを中心に解説します。
- 建設業におけるマニュアルの重要性を再確認したい
- マニュアルの正しい作成方法を知り、現場で活用されるようにしたい
- ITツールでマニュアルを簡単に作成したいが、どれが良いか分からない
という方はこの記事を参考にすると、建設業におけるマニュアルの正しい作成手順が分かるほか、自社にマッチしたツールも見つけられます。
目次
建設業におけるマニュアルの意義とは
建設業でマニュアルが重要なのは、業務の標準化や効率的な人材育成ができるためです。
建設業では重機や工具などを扱うため、使い方が人によって異なるとケガや事故につながってしまいます。しかし、マニュアルがあればやり方を統一できるので、事故防止はもちろん作業の品質がばらつく心配もありません。
また、マニュアルをノウハウとして蓄積すると、作業手順をわざわざ担当者に質問する手間が省けます。その結果、新人教育もスムーズになるのです。
【無料あり】建設業でのマニュアル作成に役立つツール4選
以下では、建設業でのマニュアル作成に役立つおすすめのツールを4つご紹介します。
マニュアルは作成して終わりではなく、チームに活用されなければなりません。しかし、手書きでのマニュアルでは記載や修正に時間がかかるうえ、更新や修正が重なれば徐々に見づらくなってしまいます。
そこで、テキスト入力によって視認性を保てる「ITツール」を使えば、全体への共有も一か所で完結します。とはいえ、建設業界ではアナログに慣れた現場も多いことから、多機能なITツールではメンバーが使いこなせない恐れもあるので注意しましょう。
したがって、建設業界では「必要な機能に過不足のないシンプルなITツール」が必須なのです。つまり、非IT企業の65歳の方でも、マニュアルをはじめとした情報を簡単に作成・共有できる「Stock」一択だと言えます。
Stockの「ノート」にはテキストや画像、ファイルを残せるので、分かりやすいマニュアルが簡単に作成できます。さらに、カテゴリに応じてノートを「フォルダ」で振り分ければ、情報が入り乱れる心配もありません。
【Stock】最も簡単にマニュアルを作成・管理できるツール

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
【TEんDO】マニュアルを自動で作成できるツール

<TEんDOの特徴>
- 豊富な編集機能がある
- さまざまな形式で出力できる
ズーム機能や音声入力機能など、さまざま方法で編集できます。
WordやExcel、PowerPointなど、マニュアルをさまざまな形式で出力できます。
<TEんDOの注意点>
- マニュアル作成以外には使えない
マニュアル作成に特化しており、タスク管理やメッセージのやりとりはできません。
<TEんDOの料金体系>
- ベーシックプラン:74,800円/ユーザー/月(月払い)
- オプション:16,280円/ユーザー/月(月払い)
【Dojo】豊富なテンプレートが備わるマニュアル作成ツール

<Dojoの特徴>
- マニュアルを短時間で作成できる
- 使い方を教える時間が省ける
テンプレートや自動入力の機能により、マニュアルを短時間で作成できます。
オンラインで使い方を学習できるため、社員の教育に時間がかかりません。
<Dojoの注意点>
- ライセンスキーがUSB
DojoにアクセスするためのライセンスキーはUSBであるため、紛失のリスクがないように管理しなければなりません。
<Dojoの料金体系>
- 詳細な料金は要問い合わせ
【Teachme Biz】伝わりやすいマニュアルを作成できるツール

<Teachme Bizの特徴>
- マニュアルを簡単に作成できる
- アクセスログを見られる
テンプレートに沿ってマニュアルを作成できるほか、手順が表示されるので初心者でも安心です。
アクセスログによって、マニュアルが活用されているかを確かめられます。
<Teachme Bizの注意点>
- 料金が高めに設定されている
料金が50,000円/月~のため、コストを抑えたい場合は不向きだと言えます。
<Teachme Bizの料金体系>
- スタータープラン:50,000円/月
- ベーシックプラン:100,000円/月
- エンタープライズプラン:300,000円/月
建設業におけるマニュアルの基本項目
一般的に、建設業におけるマニュアルの基本項目は以下の通りです。
- 作業の目的
- 作業のタイミング
- 作業の大まかな流れ
- 詳細な作業手順
- 作業のコツや注意点
- 確認事項などのチェックリスト
上記の項目を抜け漏れなく記載すれば、読み手の認識がズレることなく「活用されるマニュアル」にできます。
4ステップ|建設業のマニュアル作成手順
ここでは、建設業のマニュアル作成手順を4ステップで解説します。マニュアルをスムーズに作成するためにも、以下の手順で進めましょう。
(1)対象の業務を選定する
まずは、マニュアルの対象となる業務を選定します。
急にすべての業務を標準化すると、かえって現場の混乱を招く恐れがあります。そのため、標準化すべき業務に優先度をつけて、段階的に進めるのが大切です。
たとえば、「日報や工程表の書き方」や「安全点検の手順」など、属人化しやすい業務から優先してマニュアルを作成しましょう。
(2)業務フローを整理する
次に、対象の業務が決まったら、業務フローを整理します。
業務フローを整理すれば、作業の全体像を掴めるので、作業者は適切な目標設定ができます。また、認識齟齬防止のために、抽出したフローに過不足がないか、現場の担当者に適宜ヒアリングをしましょう。
加えて、フローチャートや実際の機材の写真などを挿入すると、作業者はより具体的なイメージを持てるようになります。
(3)項目を抜け漏れなく記載する
業務フローの整理が完了したら、マニュアルの項目を抜け漏れなく記載します。
作業の目的やタイミング、確認事項などを抜け漏れなく記載すれば、全員がミスなく作業を進められます。ただし、項目が分かりづらければ次第に利用されなくなってしまうため、適宜改行を入れるなどの工夫をしましょう。
また、「専門用語には解説をつける」「各作業にはコツや注意点も記載する」など、経験の浅い従業員に向けた配慮も大切です。
(4)見直し・修正をする
最後に、マニュアルの見直し・修正をします。
マニュアルは一度作成して終わりではなく、作業に変更点があればその都度反映しなければなりません。そのため、現場からのフィードバックを受けつつ、必要に応じて見直しや修正をすべきなのです。
とはいえ、紙のマニュアルでは、修正が重なると見づらくなるため「ITツール」を使うのが効果的です。ITツールであれば見直しや修正の跡が残らないのはもちろん、全体への共有も瞬時にできます。
ただし、アナログな手法に慣れている建設現場で、多機能なITツールを導入すると、従業員が使いこなせず放置される事態になりかねません。一方、ITに詳しくない65歳の方でも即日で使える「Stock」であれば、一切のストレスなく情報を蓄積・共有できます。
建設業におけるマニュアルの意義・作成手順・ツールまとめ
ここまで、建設業におけるマニュアルの意義や作成手順、おすすめのツールを中心にご紹介しました。
建設業におけるマニュアルでは、業務の標準化や効率的な人材育成に役立たせるために、読み手に分かりやすい構成が求められます。また、マニュアルは対象の業務を選定したうえで、業務フローを整理したり定期的に見直したりするのが大切です。
しかし、伝わりやすいマニュアルを作成しても、チームで活用されなければ意味がありません。そこで、作成から共有に時間のかかる紙ではなく、テキストでマニュアルを作れる”ITツール”を使いましょう。
ただし、現場にはITが苦手なメンバーもいるので、多機能なITツールでは正しく使われない恐れがあります。したがって、必要な機能に過不足がなくシンプルな「Stock」が、建設業界に最適なのです。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」でマニュアルを作成・共有し、自社の業務を標準化しましょう。