激しいトレンドの変化に対応するため、今日では多くの企業で「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」が進められています。しかし、DXの意味や推進する理由は十分に社会へ浸透していないのが現状です。
そのため、DXに関することがあまり分からず、結果としてDX化に踏み込めていない担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、DXの意味やメリット、推進事例を中心にご紹介します。
- DXの意味や内容を詳しく把握できていない
- DXの推進によってどのようなメリットがあるのか知りたい
- DXの成功事例をもとに、自社でも活かせるポイントを押さえたい
という方はこの記事を参考にすると、DXの意味や推進すべき理由が分かるほか、自社で円滑にDXを進められるようになります。
目次
DXの意味とは
ここでは、DXの定義や類義語との違いを解説します。これまでDXに対する理解が曖昧だった方は必見です。
経済産業省の定義
経済産業省はDXを以下のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」引用:DXレポート
上記を一言でまとめると、DXは「IT技術により業務を変革させて競争優位性を得ること」になります。
デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い
DXの類義語に「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」があります。
デジタイゼーションは”業務をデジタル化してデータを蓄積すること”を指し、デジタライゼーションは”蓄積されたデータをもとに業務フローを改善すること”を指します。つまり、両者には手段と結果の違いがあるのです。
また、DXは”変革したビジネスモデルから新たな価値を社会に提供すること”を指すので、デジタイゼーションとデジタライゼーションはともにDX化の手段になります。
DXが注目される理由
DXに注目される理由には「2025年の崖」があります。2025年の崖とは、2018年に経済産業省が「DXレポート」で指摘した問題です。
DXレポートでは「2025年までに日本の企業がDXを実現できない場合、最大で年間12兆円もの損失が生じる可能性がある」と指摘しています。このような経済損失を抑えるためにも、今日ではDX推進が求められているのです。
しかし、2021年に経済産業省が実施したアンケートによると、国内上場会社のうちDX推進を具体化できている企業は約半数に留まっているのが現状です。万が一自社が当てはまっている場合は、早急に既存システムを見直しましょう。
DX推進による3つのメリット
以下では、DX推進によるメリットを3つ解説します。これまでメリットが分からずDX化に躊躇していた方は必見です。
(1)生産性を向上できる
まずは、DX推進によるメリットとして生産性の向上があります。
DXにより作業や情報がデジタル化されると、これまで手作業だった業務の負担が大幅に軽減されます。さらに、業務プロセスも最適化されることから、重要プロジェクトに充てるリソースもより多く確保できるのです。
以上のようにDXで業務プロセスが改善されれば、限られたリソースを有効活用しながら生産性を高められます。
(2)コストを削減できる
次に、コストを削減できるのもDX推進のメリットです。
長期的に同一のシステムを使い続けていれば、システムの劣化や維持費の高騰といった問題が起こりかねません。また、既存システムを管理できる人材が転職・退職でいなくなり「誰もシステムのトラブルに対処できない」となる恐れもあります。
しかし、DXによって最新のシステムを導入すれば、システムに不具合が生じるリスクを軽減できます。その結果、トラブル対応に無駄なコストを割く必要もなくなるのです。
(3)新たなビジネスへ展開できる
最後に、DX推進により新たなビジネスへ展開できるメリットもあります。
たとえば、DXの一環として情報共有に役立つクラウドツールを導入すると、あらゆる情報を一カ所で管理できます。その結果、顧客動向も正確に分析でき、新たな商品やプロモーションの発案にもつながるのです。
以上のように、DXにより情報共有が円滑化すれば、顧客に対してより適切なアプローチができるようになります。
DXの推進事例3選
以下では、DXの推進事例を3選ご紹介します。事例をもとにDXの具体的なイメージを掴みたい方は必見です。
事例1|横浜銀行
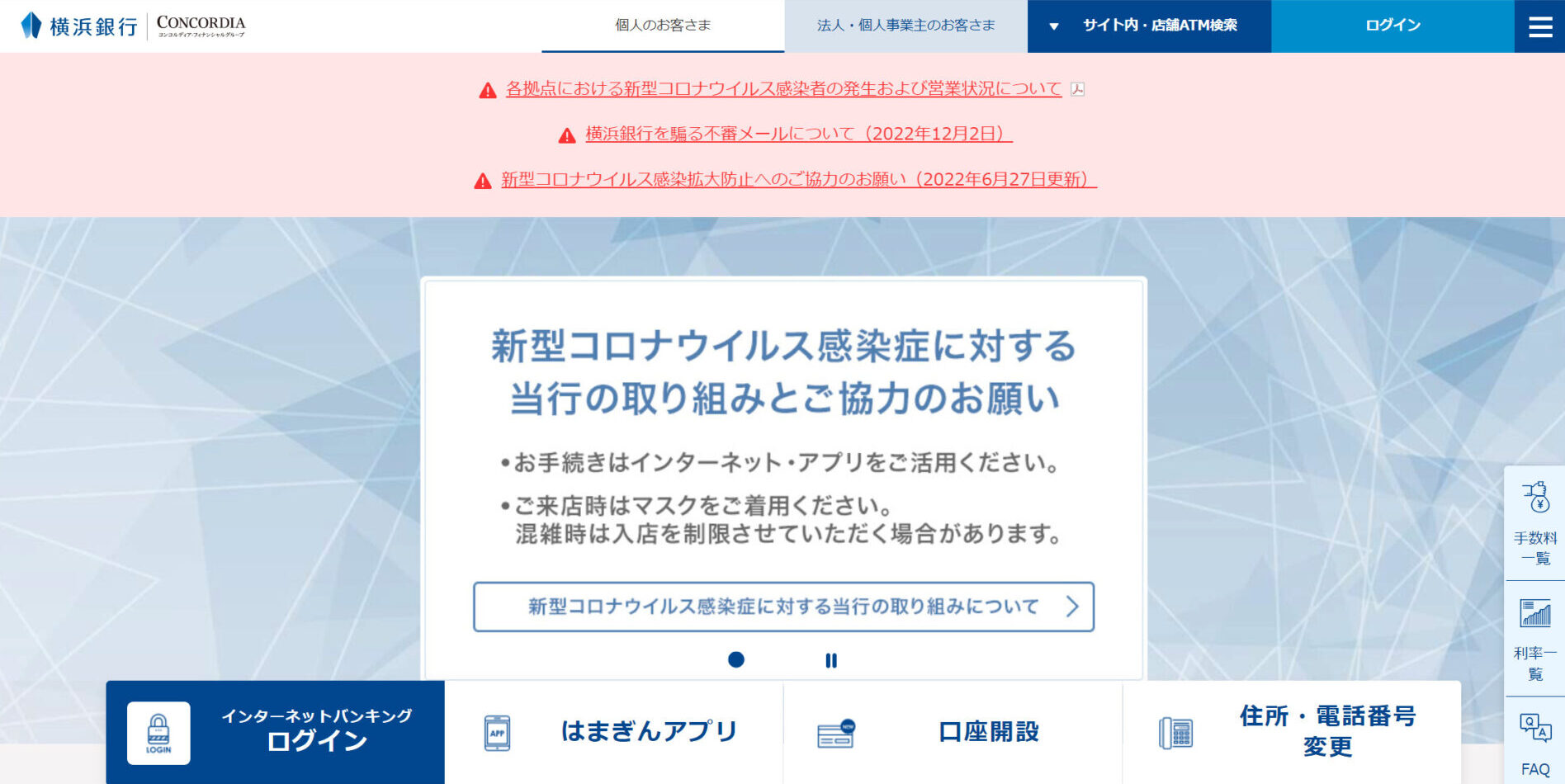
横浜銀行は、2020年10月から「AI不正・リスク検知サービス for Banking」を稼働しています。
当行では、巧妙化する金融犯罪に対応するためモニタリング業務を強化しました。具体的には、人間では分かりづらい不正取引も検知できるAIシステムを導入したのです。
その結果、あらゆる金融犯罪を未然に防げるようになったのはもちろん、調査対象となる口座も30~40%減らせました。
参考:横浜銀行の事例
事例2|ユニメイト

株式会社ユニメイトは、ユニフォームの販売やレンタル事業をしている企業です。
当社では、ヒューマンエラーによるミスが頻発し、返品や交換といった無駄な労力がかかっている課題がありました。そこで、AIの画像認識システムを開発したのです。
その結果、手作業で採寸をする手間が省けて細かなミスが減ったほか、返品・交換にかかるコストや在庫の削減にもつながりました。
参考:ユニメイトの事例
事例3|株式会社ハピネス
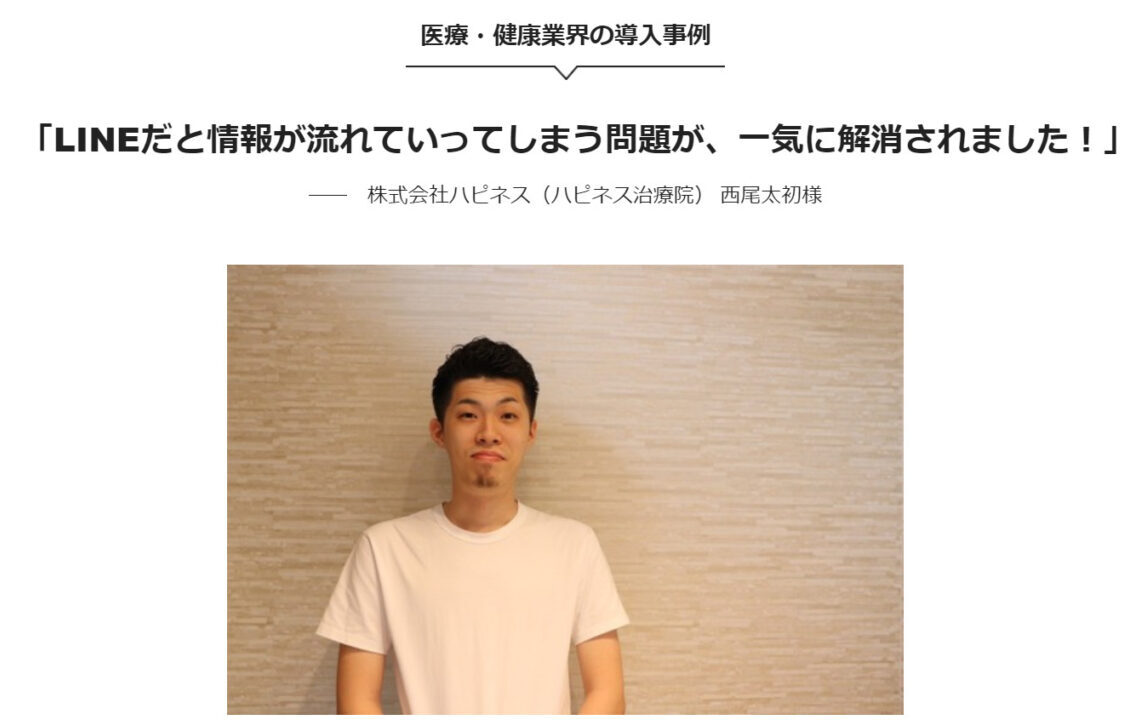
株式会社ハピネスは、訪問型のはり灸マッサージ事業をしている企業です。
当社ではLINEで情報共有をしていましたが、情報が流れてしまい営業先との商談記録などが見返しづらい課題がありました。そこで、あらゆる情報を簡単に残せる「Stock」を導入したところ、目的の内容へすぐにアクセスできるようになったのです。
また、情報が蓄積されることから「過去に誰とどのような商談をしたか」も明確に分かるようになり、その後の営業戦略にも役立てられました。
参考:株式会社ハピネスの事例
【担当者必見】最も簡単にDXを推進できるツール
以下では、最も簡単にDXを推進できるツールをご紹介します。
DXを推進するには、チーム全体で活発な情報共有が必須です。しかし、最新のシステムを導入しても情報共有が遅ければ認識の齟齬が起こり、かえって業務が非効率となりかねません。
そこで、すべての情報を一元化する”クラウドツール”を使えば、情報のやりとりが常にリアルタイムでできます。ただし、操作が複雑なツールでは使い方を教えるのに時間がかかるので「ITリテラシーが低くても直感的に扱えるツール」でなければなりません。
すなわち、DXを成功させるには、非IT企業の65歳以上でも説明なしで使えるほどシンプルな「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」であらゆる情報が簡単に蓄積されるほか、ノートごとに「メッセージ」「タスク」が紐づいているので案件ごとに情報管理できます。また、話題が錯綜しないためコミュニケーションも円滑に図れるのです。
非IT企業の65歳が即日で使いこなせるツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
DXをサポートする技術・ツール例
ここでは、DXをサポートする技術やツール例をご紹介します。以下を活用して自社のDX化に役立てましょう。
| 技術・ツール名 | 内容 |
|---|---|
| IoT(Internet of Things) |
スマートフォンや遠隔操作システムなど、ネット接続・相互通信ができる技術です。 |
| AI(Artificial Intelligence) |
自動運転など、学習機能によって人間よりもスピーディに情報処理できる技術です。 |
| RPA(Robotic Process Automation) |
ロボットであらゆる業務プロセスを自動化できるツールです。 |
| バックオフィスツール |
勤怠管理や給与計算、請求書の発行といった業務を簡略化できるツールです。 |
| クラウドツール |
あらゆる情報を一カ所に集約でき、ツールを併用する手間が省けるツールです。 |
上記のツールを活用すれば、DXの浸透によりあらゆる業務負担が軽減されます。
自社は大丈夫?DX推進における3つの課題
ここでは、DX推進における課題を3つご紹介します。DXは多くの面で効率化が図れる一方、以下の点に注意しましょう。
課題1|経営者層の意識が低い
まずは、DX推進の課題として経営者層の投資意識の低さが挙げられます。
日本企業の99%は中小企業であり、資金力の低い零細企業も多いです。そのため、現状のアナログな業務に慣れていれば、DXへの投資に手が回らない可能性もあります。
したがって、経営層を説得する際は「DX推進により〇%のコスト削減になる」「〇〇の点で競合と差をつけられる」のように、DXのメリットを正しく理解させるべきです。
課題2|既存システムがレガシー化している
既存システムがレガシー化しているのも、DX推進の課題です。
レガシー化とは、既存システムの維持・管理コストが高額になっている状態を指します。また、レガシー化から脱却するには既存システムを刷新しなければならず面倒なのです。
以上のように、多くの日本企業では「既存システムがレガシー化しているものの、システムの移行は複雑で面倒」といった点でDXを推進できていません。
課題3|高いITリテラシーが求められる
DX推進には高いITリテラシーが求められる課題もあります。
とくに、非IT企業では社内システムの管理を外部に委託しているケースが多いので、ノウハウが蓄積されず既存システムをすぐに移行できないのが現状です。
しかし、ITに詳しくない人でも即日で使いこなせる「Stock」であれば、操作を教える手間が一切かかりません。そのため、既存システムからも簡単に移行できます。
DXの意味や事例まとめ
ここまで、DXの意味や推進事例を中心に解説しました。
DXは”ITにより業務を変革して競合優位性を得ること”を意味します。また、DXを推進するうえではあらゆる情報を一元管理する「クラウド管理ツール」を使い、チームで円滑なやりとりを促す必要があるのです。
ただし、複雑なツールではITリテラシーの低い社員が使いこなせず、かえって業務が非効率となりかねません。そのため、ツールを選定する際は必ず「シンプルで直感的な操作ができるか」を判断すべきです。
結論、自社のDX推進には、非IT企業の65歳でもストレスなく使いこなせて、必要な機能に過不足ない「Stock」が最適なのです。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」でDXを実現し、自社の業務効率をアップさせましょう。



