社内コミュニケーションは、チーム全員の作業状況を可視化して把握するのに不可欠です。また、社内コミュニケーションを活性化させれば、業務を円滑に進められます。
とはいえ、社内コミュニケーションの課題は企業やチームによって異なるため「情報共有の促進に最適な施策が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社内コミュニケーションを活性化させる方法を中心にご紹介します。
- 部署間の情報共有が不足しており、仕事がスムーズに進まない
- 部内で従業員同士のコミュニケーションを増やしたい
- 社内コミュニケーションの活性化を簡単に実現したい
という方はこの記事を参考にすると、自社の社内コミュニケーションを活性化させる効果的な取り組みが分かります。
目次
社内コミュニケーションとは?

社内コミュニケーションとは、社内のチームや部署間、従業員間で日頃から実施されている会話、情報共有、情報交換といったやりとりを指します。
業務上のやりとりだけでなく、雑談やミーティング、社内イベントといったさまざまな交流を含めた概念が社内コミュニケーションです。とくに、近年はリモートワークの普及によって社内コミュニケーションの重要性が再確認されています。
社内コミュニケーションの必要性

ここでは、社内コミュニケーションが必要な理由を3つご紹介します。これまで十分に社内コミュニケーションをとっておらず、情報共有が滞っていた担当者の方は必見です。
(1)業務効率化が促進される
社内コミュニケーションが必要な理由の一つは、業務効率化の促進です。
たとえば、部下が分からない仕事についてすぐに上司へ質問できるほどコミュニケーションが活発であれば「何時間も一人で試行錯誤する」という無駄な作業がなくなります。
以上のように、業務の無駄を省いて効率化するために、スムーズな社内コミュニケーションが求められるのです。
(2)社員の考えが見えやすくなる
社内コミュニケーションには従業員の考えが見えやすくなる効果もあります。
たとえば、従業員の作業状況をこまめに報告する環境では、遅れが発生しても「どのように日程調整するのが良いか」といった質問や意見を躊躇なく出せます。
このように、社内コミュニケーションの徹底は従業員の考えを引き出し、意見交換しやすいチーム作りに役立つのです。
(3)社員の離職率を下げる
従業員の離職率が下がるのも、社内コミュニケーションをすべき理由のひとつです。
社内コミュニケーションが活性化すると従業員の些細な変化が分かり、悩みを抱えている従業員を把握しやすくなります。そして、悩みを解消するために対応でき、離職率低下につなげられるのです。
このように、従業員が悩みを共有できず職場にストレスを感じるのを防ぐためにも、社内コミュニケーションを頻繁にとりましょう。
社内コミュニケーションが不足すると何が起こる?

社内コミュニケーションが不足すると、以下のようなさまざまな問題が生じます。
- 仕事のミスに気づきにくい
- 意思決定が遅れる
- 離職率が高くなる
コミュニケーションが不足すると、従業員が「どの作業を、どこまで進めているのか」が不透明になり、結果的にミスや遅れに気づきにくい状況になります。
意見交換や情報共有が乏しい職場では議論が活発に進まず、意思決定が遅れる可能性があります。
日頃からコミュニケーションをとれていないと、人間関係の悩みやモチベーションの低下につながりやすく、結果的に離職率を高める可能性があります。
以上のように、社内コミュニケーションの不足は仕事や会社全体に大きなリスクをもたらすため、早急な改善が求められるのです。
社内コミュニケーションを活性化させる取り組み4選

ここでは、社内コミュニケーションを活性化させる取り組みを3つご紹介します。自社に合った方法を選んで実践しましょう。
アイデア1|社内コミュニケーションツール
一つ目は、メッセージのやりとりによって情報共有を円滑にする「社内コミュニケーションツール」の導入です。
社内コミュニケーションツール上では、時間や場所を問わずリアルタイムで気軽にやりとりできます。そのため、「相手のタイミングを見計らって連絡する」や「CcやBcc、件名を設定する」といった無駄な作業を省いて業務効率を向上する効果があるのです。
ただし、チャットツールのように情報が埋もれて流れてしまうツールでは、あとから目的の情報を瞬時に探せないストレスがあります。そのため、あらゆる情報を簡単かつ確実に蓄積できる「Stock」のように情報が流れないツールを選びましょう。
アイデア2|社内報
二つ目の取り組みは、「社内報」です。
社内の出来事や共有事項をまとめた社内報の発行は、他部署の取り組みを把握したり、面識のない従業員について知ったりするきっかけになります。その結果、コミュニケーション不足による「誰が何をやっているのか分からない」という状況を改善できるのです。
とくに、従業員数が多く事業範囲が多岐にわたる大企業で効果的な取り組みです。
アイデア3|1on1ミーティング
三つ目の取り組みは、1on1ミーティングです。1on1ミーティングとは、上司と部下が一対一で話し合う定期的な面談を指します。
1on1ミーティングを実施すれば、部下と直接顔を合わせながらやりとりできるため、些細な悩みや不満を把握しやすくなります。また、リモートワーク中でも、Web会議システムを使って実践できるのがメリットです。
さらに、ミーティング中に日頃の業務に対するフィードバックをすることで、部下のモチベーションを向上させる目的もあります。そのため、単なるコミュニケーションの機会だけでなく、部下の成長を促進する目的でも効果的なのです。
アイデア4|フリーアドレス制度
四つ目の取り組みは、フリーアドレス制度です。
フリーアドレス制度とは、従業員のデスクを固定せず、空いている座席や社内のオープンスペースなど自由な場所で作業できる制度を指します。
フリーアドレス制度を取り入れることで、チームメンバー以外の従業員と顔を合わせる機会が増え、部署やプロジェクトを超えたコミュニケーションが実現するのです。
【必見】簡単に社内コミュニケーションを活性化させる方法

ここでは、簡単に社内コミュニケーションを活性化させる方法をご紹介します。
そもそも、社内コミュニケーションの多くを占めるのは日常業務でのやりとりです。したがって、「情報共有そのもの」のストレスを解消しなければ、根本的な解決にはつながらないのです。
したがって、定型文やCc不要でストレスのない「情報共有ツール」を使うのが最も効果的です。ただし、チャットツールのように情報が流れるものはアクセスするのが面倒なので、あらゆる情報を流さずにストックするツールを選びましょう。
結論、社内コミュニケーションの活性化に最適なのは、あらゆる情報を確実に蓄積して、活発なコミュニケーションがリアルタイムにとれる「Stock」一択です。
Stockには重要な情報を書き残せる「ノート」があり、ノート紐づいた「メッセージ」でスムーズにやりとりできます。また、直感的な「フォルダ」で情報をテーマごとに整理するので、目的の情報をすぐに探し出せるのです。
非IT企業の従業員でも使える情報共有ツール「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
社内コミュニケーションの成功事例3選
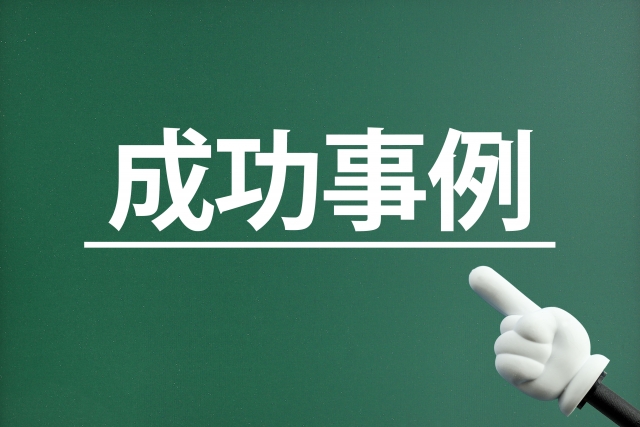
ここでは、社内コミュニケーションに成功した企業の事例を3つご紹介します。自社の社内コミュニケーション活性化につなげるためにも、以下の成功事例を参考にしましょう。
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、家庭用ゲームコンテンツや業務用ゲーム機器、モバイルコンテンツの企画開発販売をしている企業です。
同社では、部署の垣根を超えたコミュニケーションのしづらさに課題がありました。部署内のコミュニケーションは各フロアでとれている一方、部署を越えたやりとりが不十分で、自社の全体像を把握できていなかったのです。
そこで、オフィスにリラックススペースやソロワークスペースを新設し、場所に囚われず自由に仕事できるようにしました。その結果、部署を越えたコミュニケーションの機会が増えたのです。
株式会社資生堂
株式会社資生堂は、化粧品の開発や販売をしている企業です。
同社では、働き方改革の推進にともなって、ITを活用した情報共有やコミュニケーションの推進に取り組んでいました。しかし、従業員のITリテラシーが追いついていないことに課題を感じていたのです。
そこで、ITに詳しい若手社員が経営トップのメンター(指導者)となるリバースメンター制度を導入しました。その結果、役員のITリテラシーが向上し、ITの活用方法を提案する若手社員の評価が高まったのです。
参考:株式会社資生堂の事例
クックパッド株式会社
クックパッド株式会社は、料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」を運営している企業です。同社では従業員同士のコミュニケーションに課題がありました。
そこで、オフィス移転に伴い30~40名の社員が同時に料理を作れる巨大なキッチンスペースを設置しました。その結果、複数人での調理を通した気軽なコミュニケーションがとれるようになったのです。
社内コミュニケーションを活性化させるメリット

以下では、社内コミュニケーションを活性化させるメリットを2つご紹介します。「何か施策を打ちたいが、効果があるのか不安で踏み出せない」という担当者の方は必見です。
(1)モチベーション向上につながる
一つ目のメリットは、従業員のモチベーション向上につながることです。
活発なコミュニケーションがとられている会社では、従業員が積極的に自分の意見を発信する企業文化が作られます。その結果、仕事へ主体的に取り組みやすくなり、モチベーションの向上が期待できるのです。
さらに、仕事上のやりとりだけでなく、雑談や社内イベントでのコミュニケーションが人間関係を良好に保つ効果もあります。
(2)生産性が向上する
二つ目のメリットは、仕事の生産性が向上することです。
たとえば、「ある従業員のタスクが遅れている」という場合、情報共有が活発な職場であれば、瞬時に把握してほかのメンバーへ作業を依頼できます。一方、日頃からこまめな進捗共有が実施されていないと、そもそもタスクの遅れに気づけない可能性があるのです。
以上のように、コミュニケーションを活性化させることは、チーム内で効率的に仕事を進めるのに役立ちます。
社内コミュニケーションを活性化させる方法まとめ
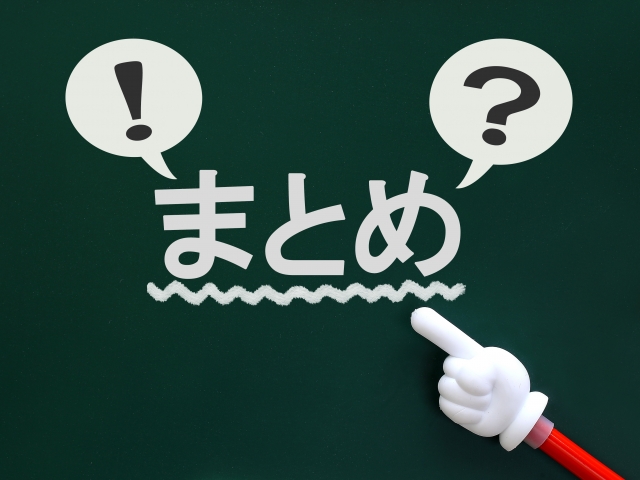
ここまで、社内コミュニケーションを活性化させる方法を中心に解説しました。
社内コミュニケーションを活性化するのに最適な方法は、リアルタイムで簡単にメッセージをやりとりできる”情報共有ツール”を導入して、日頃の情報共有からスムーズにしていくことです。
ただし、目的の情報がほかの内容に埋もれて流れるツールでは、重要なメッセージを見逃しかねず、かえってコミュニケーションに悪影響を及ぼすことがあります。そのため、「情報をテーマごとに蓄積できるツール」を選びましょう。
たとえば、今回ご紹介したStockは、非IT企業の65歳以上の従業員でも使えるほど簡単なうえ、情報を流さず蓄積するツールです。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」で社内コミュニケーションを活性化し、スムーズな情報共有を実現しましょう。



