DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進が求められている今日では、DXの導入をサポートする「DX支援サービス」を利用する企業も増えています。
しかし、サービスによって具体的にどのような支援を受けられるのか分からない担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、DX支援サービスの事例や選定ポイントを中心にご紹介します。
- DX支援サービスでどのようなサポートを受けられるのか知りたい
- 他社の事例をもとにDX支援サービスの明確なイメージを掴みたい
- DX支援サービスの選定ポイントを押さえ、自社に最適なものを活用したい
という方はこの記事を参考にすると、DX支援サービスによる実際の効果が分かるほか、自社に最適なサービスも見つけられます。
目次
DX支援サービスとは
DX支援サービスは「技術支援サービス」と「ビジネス変革支援サービス」に分けられます。それぞれの特徴を押さえたい方は必見です。
技術支援サービス
技術支援サービスは、ネットワークを経由しながらモノを遠隔で確認・操作できるIoT(Internet of Things)の活用や、システムの構築を支援するサービスです。
技術支援サービスでは新技術の導入時はもちろん、システムの導入後も自社で適切な維持・管理ができるように、専門家によって徹底したサポートがされます。
ただし、DXを実現するには導入した技術を正しく活用しなければならないので、新技術を用いた新しい業務フローを構築する必要があるのです。
ビジネス変革支援サービス
ビジネス変革支援サービスは、DX人材の育成やデジタル戦略の策定、組織体制の変革といった将来的なDX実現を支援するサービスです。
本サービスでは、デジタル技術によるビジネスモデルの設計から実行支援のコンサルティングまでのサポートを受けられます。つまり、”技術を効果的に使うにはどうすべきか”にフォーカスしているのです。
また、DX人材を育成すれば専門業者に外注するコストも省けるので、リソースを多く確保するうえでもビジネス変革支援サービスは多くの企業で利用されています。
政府のDX支援
以下では、政府によるDX支援の概要を解説します。これまで政府からどのようなDX支援がされているのか分からなかった方は必見です。
DX産業指標とは
DX産業指標とは、企業を4つの類型に分類してそれぞれが目指すべき姿を明らかにしたものです。経済産業省は以下の説明をしています。
「デジタル産業の企業類型への変革を推進するためには、自社がデジタル産業の企業に該当するのかどうかを判断できる必要がある。また、該当する場合には、その成熟度を評価できることが望ましい」引用:DXレポート2.1
上記をまとめると、DX産業指標は各企業に”自社がDXに適した類型であるか”を定量的に把握させ、効果的な施策を促すために設置されたと言えます。
中小企業向けのDX補助金制度
中小企業向けの補助金制度は以下の2つに分けられます。
- ものづくり補助金
- IT導入補助金
開発や生産プロセスを改善するための設備投資をサポートする補助金です。
参考:ものづくり補助金とは
自社に最適なITツールへの投資をサポートする補助金です。
参考:IT導入補助金とは
以上のような補助金制度により、今日では多くの中小企業で進められています。しかし、資本金や従業員数によっては対象外の場合もあるので申請の際は注意が必要です。
DX支援サービスの事例4選
以下では、DX支援サービスの事例を4つご紹介します。他社事例をもとにサービスの活用イメージを掴みたい方は必見です。
事例1|NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社は、業務効率化の方法を伝える「DX支援コンサルティング」を提供している企業です。
同社では、実際にDXを実現したノウハウに基づいて細かなコンサルティングを実施しています。具体的には、電子署名による紙書類・印鑑からの脱却やクラウドサービスによる情報の一元化といった施策があります。
また、サポート体制も充実しているため、急にシステム導入をする場合もすぐに支援を受けられるのです。
事例2|みずほリサーチ&テクノロジーズ

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、企業の成長戦略を支援する「DX支援コンサルティング」を提供している企業です。
同社のサービスは「DX構想策定に関する支援」や「DX教育に関する支援」など細かく分かれています。そのため、自社に適した支援サービスも見つけやすいのです。
以上のように、同社では各企業におけるDXのプロセスを大きく簡略化する仕組みを構築しています。
事例3|富士通
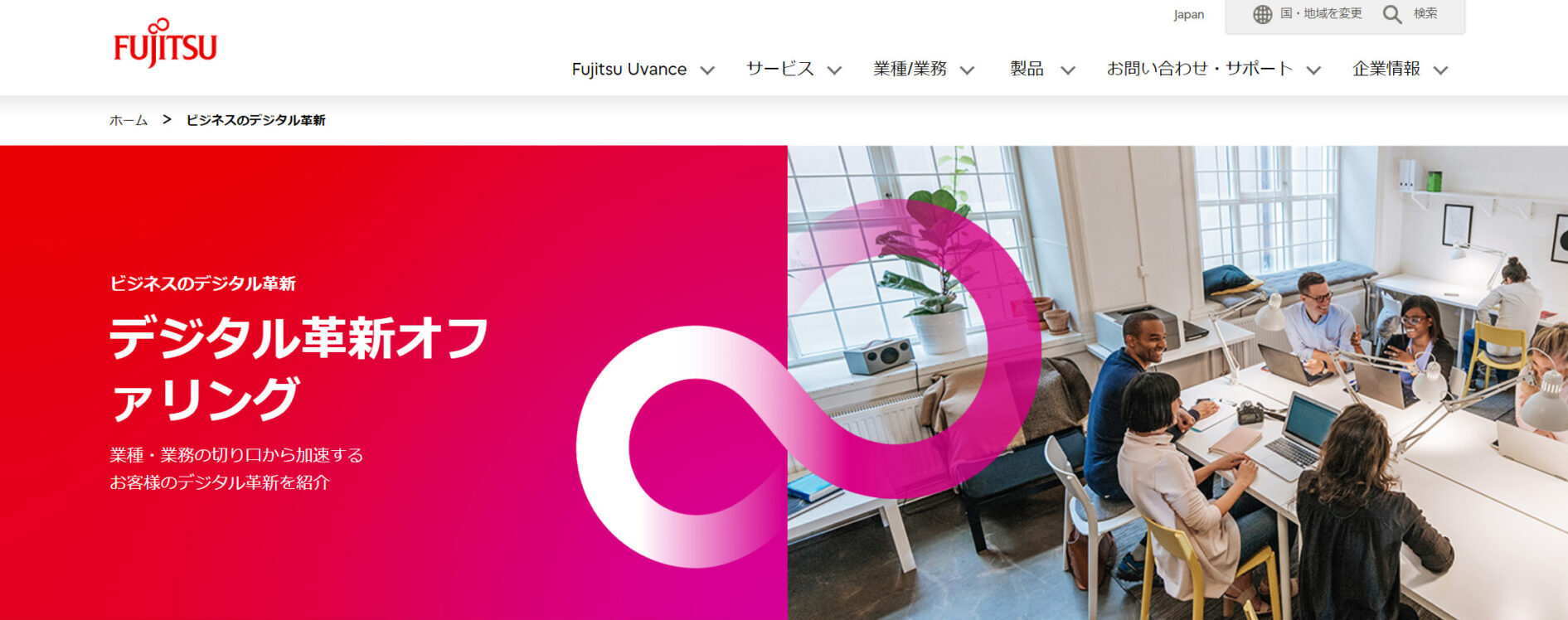
富士通株式会社は、業種・業務別に適したDX推進支援をする「デジタル革新オファリング」を実施している企業です。
同社では、デジタルによる革新を「事業」「顧客関係」「組織・働き方」「社会・経済」の4つに分類しています。さらに「小売」や「金融」をはじめ15の分野に細分化するなど、あらゆる利用シーンを想定しているのです。
そのため、自社が実際にDXを進める過程はもちろん、DXが実現したあとのイメージもより明確になります。
事例4|合同会社アクラス

合同会社アクラスは、訪問介護をはじめ4つの福祉事業を展開している企業です。
同社では患者の情報をタイムライン形式のツールで共有していましたが、内容が次々と流れてしまう課題がありました。そこで、目的の情報を簡単に残せるサービス「Stock」を導入したところ、情報へのアクセススピードが大幅に上がったのです。
また、StockはITに詳しくなくても簡単に使いこなせるほどシンプルなため、使い方を覚える時間も一切かかっていません。
【担当者必見】DXの実現に最適なサービス
以下では、DXの実現に最適なサービスをご紹介します。
DX支援サービス多くは、徹底したサポートが受けられるものの高額なケースもあります。それゆえ、自社の予算に収めるためにも”より安価でDXを進められるサービス”が求められるのです。
ただし、操作が複雑で分かりにくいサービスでは次第に使われなくなってしまいます。したがって、継続的に運用していくには「ITリテラシーが低くてもストレスなく使いこなせるサービス」でなければなりません。
結論、DXの実現には、非IT企業の65歳でも簡単に使えるため、そもそもサポートを受ける工数がかからない「Stock」が最適です。
Stockの「ノート」に情報を記載すれば、メンバーへ即座に共有できます。また、ノートごとに「メッセージ」「タスク」を紐づけられるので情報が混在せず、万が一問題が起きた際にも1営業日以内に対応する充実のサポート制度を整えています。
非IT企業の65歳でも即日で使えるサービス「Stock」

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
DX支援サービスにおける選定ポイント3選
ここでは、DX支援サービスにおける選定ポイントを3つご紹介します。サービスの導入後に「思っていたものと違っていた」とならないためにも、以下の点を押さえましょう。
(1)自社の予算に収まるか
まずは、DX支援サービスの選定ポイントとして、自社の予算に収まることがあります。
DX支援サービスではDXの構想から人材の教育までをサポートするため、比較的高額なものも多いです。仮にサービスに必要以上のコストをかけてしまうと、ほかの業務に割くリソースも圧迫しかねません。
したがって、必ず自社の予算からサービスの導入可否を判断すべきなのです。
(2)継続してサポートを受けられるか
継続してサポートを受けられることも、サービスの重要な選定ポイントです。
システムに問題が起きた際に契約期間が終了していれば、業務のスピードが大きく停滞してしまいます。また、契約期間を延長すれば長期的なサポートを受けられるものの、コストも多くかかるため予算を圧迫しかねません。
そのため、サービスの選定時には長期的なサポートであるかを必ず判断し、万が一システムトラブルが起きても迅速に対応できるようにしましょう。
(3)簡単に使いこなせるか
最後に、簡単に使いこなせるサービスであるのも大切です。
操作が複雑なサービスでは、使い方を覚えるのに手間がかかるだけでなく情報管理に不備が出る恐れもあります。このような事態を防ぐには「ITリテラシーが低くても即日で使えるほど簡単なツール」が求められるのです。
たとえば、必要な機能に過不足ないシンプルな「Stock」を使うと、直感的な操作性により業務にミスが出る心配がありません。
DX支援サービスの事例やポイントまとめ
ここまで、DX支援サービスの事例や選定ポイントを中心にご紹介しました。
DX支援サービスを使えばDXの構想策定や人材の教育が一任できる反面、サポート期間が短かったり高額だったりするものも多いです。そのため、サービスの選定時は自社の予算に収まることはもちろん、継続したサポートを受けられるかも確認しましょう。
加えて、継続的に運用していくためには「ITリテラシーが低くても簡単に使いこなせるシンプルなサービス」にすべきです。このようなサービスであれば、使い方が分からなくなる心配もありません。
結論、DXを円滑に進めるには、非IT企業の65歳でも即日で使えるうえ、迅速なサポート体制が整っている「Stock」が最適なのです。
無料登録は1分で完了するのでぜひ「Stock」を導入し、より低コストでスピーディにDXを浸透させましょう。



