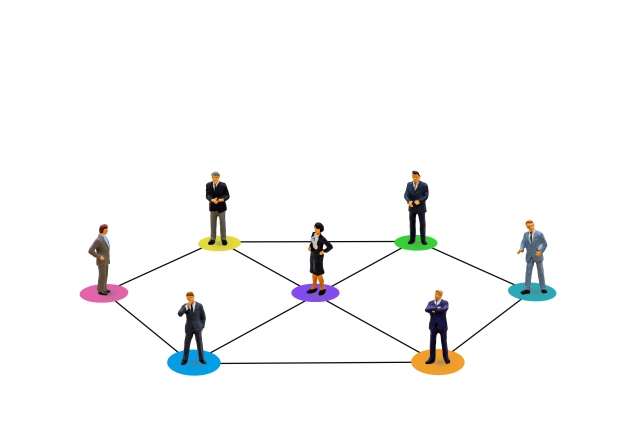企業活動を円滑にするには、他部署との連携が欠かせません。部署間連携を強化すると、社内のコミュニケーションや情報共有が促進され、業務を効率的に進められるようになります。
しかし、「他部署との連携を強化したいが、方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、他部署との連携を強化するメリットやコツ・成功事例を中心にご紹介します。
- 他部署との連携を強化して業務を円滑に進めたい
- 他社の成功事例を把握して自社の取り組みに役立てたい
- 他部署との連携を効率化できるツールがあれば知りたい
という方はこの記事を参考にすると、他部署との連携強化を具体的にイメージして取り組みを実施できます。
目次
他部署との連携を強化するメリットとは
以下では、他部署との連携を強化するメリットについて解説します。部署間連携の強化には、「業務の円滑化」や「職場環境の改善」などさまざまなメリットがあるのです。
業務が円滑に進められる
他部署との連携を強化すると、業務が円滑に進められます。
なぜなら、組織として一体感を持って、共通の目標に向かって仕事に取り組めるようになるからです。たとえば、他部署同士の連携が密になっていれば、ノウハウを共有したり、トラブルが発生した際にフォローしやすくなったりします。
また、部署間の「アイデア交換」や「活発なコミュニケーション」が促進されるので、互いの知識・経験を持ち寄って、新たな価値を創造できます。このように、部署間の連携を強化すると、社員全員が団結しやすくなり業務を円滑に進められるのです。
職場への定着率を高められる
他部署との連携が強まれば、社内コミュニケーションが促進されて、職場への定着率を高められます。
実際に、HR総研の【HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告】によると、「効果が感じられる若手人材の離職防止を意識した取組み」として、6割の企業が「社内コミュニケーションの活性化」を挙げており、社内コミュニケーションが離職防止に有効であることがわかります。
そこで、他部署との連携を強化すると、社内でコミュニケーションをとれるメンバーの幅が広がります。そのため、直属の上司を含む自部署メンバーには相談しづらい悩みも他部署メンバーに話しやすくなるので、結果として職場への定着率が高められるのです。
他部署との連携がうまくいかない3つの原因とは
ここでは、他部署との連携がうまくいかない原因について解説します。部署間連携を成功させたい企業は、以下の内容に注意して連携強化に取り組みましょう。
(1)仕事の目的を理解していない
社内メンバーが仕事の目的を理解していないと、他部署との連携も失敗しやすくなります。
なぜなら、仕事で果たす役割を理解していなければ、他部署と協力して業務を進める意義も感じられず、積極的なコミュニケーションにつながらないからです。したがって、まずは仕事の目的を社員に浸透させることが必要です。
たとえば、企業のビジョンを伝えることで仕事におけるミッションを理解させることも方法のひとつです。ビジョンが社内に浸透すれば、仕事の目的意識を持てるだけでなく、社員同士が共通認識を持ってコミュニケーションをとれるので、他部署との連携もとりやすくなります。
(2)他部署の業務状況を知らない
部署間連携がうまくいかない原因として、他部署の業務状況を知らないことが挙げられます。
なぜなら、他部署の業務状況を理解していないとコミュニケーションがとりにくくなるからです。実際に、コクヨ株式会社の【部署間コミュニケーションの現状と課題】によると、「他部署とのコミュニケーションで困っていること」として、以下の内容が回答されています。
- 気軽に話しかけられる場所がない
- 業務内容がわからず声をかけづらい
- 共通の話題がない
- 繁閑状況がわからず声をかけづらい
調査からもわかるように、「業務内容」や「繁閑状況」を把握できないと、話すべき内容やタイミングが分からず、他部署との連携は強化されません。そのため、社内の業務を可視化できる仕組みをつくって、部署間の相互理解を深める点が重要です。
(3)他部署とのコミュニケーションが不足している
他部署とのコミュニケーションが不足していると、メンバー同士の相互理解が深まらないので、連携がうまくとれません。
たとえば、HR総研の【HR総研:社内コミュニケーションに関するアンケート2022 結果報告1】によると、「社内コミュニケーション不足による業務障害の内容」として7割の企業が「部門間・事業所間の連携」を挙げており、コミュニケーション不足が他部署との連携を妨げることがわかります。
したがって、他部署との連携を強化するには、他部署の業務状況がわかる仕組みづくりが必要です。具体的には、「ナレカン」のような情報共有ツールを使って、非対面でも連絡をとりやすい体制を整えましょう。
他部署との連携を強化するコツ3選
ここでは、他部署との連携を強化するコツ3選をご紹介します。以下の内容は、部署間の連携強化の成功に欠かせないため必見です。
(1)会社の目標を浸透させる
他部署との連携を強化するためには、会社の目標を浸透させる必要があります。
なぜなら、全社員が会社の目標を理解することで、異なる部署でも同じ意識をもって業務に取り組めるようになるからです。目標に対する共通認識があれば、自然と一体感が生まれ、互いにコミュニケーションがとりやすくなります。
したがって、会社の目標を社内に浸透させ、社員が同じ方向を向いて業務に取り組めるようにすることが、自然と他部署との連携強化につながるのです。
(2)円滑なコミュニケーションを図る
他部署との連携には、円滑なコミュニケーションが欠かせません。
コミュニケーションが不足していると、他部署の業務内容や意見が把握できないため、連携がうまく取れません。その結果、誤解が生まれたり、業務の進捗に遅れが出たりしてしまう恐れがあるのです。
したがって、互いにさまざまな意見を言い合える風通しの良い環境づくりが大切です。最近では、定期的に社内イベントを行い、社員同士の交流を深める企業も増えてきています。
(3)他部署との情報共有を徹底する
他部署との情報共有を徹底することも、部署間の連携を促進するのに重要です。
それぞれの部署の業務状況やナレッジなどを共有することで、部署間の相互理解を深めることができ、結果的にコミュニケーションの円滑化にもつながります。
したがって、「ナレカン」のようにスマホやタブレットからでも気軽に情報共有できるITツールを使って、効率的かつ確実に情報を共有しましょう。
他部署との連携を効率的に強化できるツール
以下では、他部署との連携を効率的に強化できるツールをご紹介します。
他部署との連携を強化するには、他部署の業務状況を把握できる情報共有の仕組みづくりが必要です。他部署との情報共有が定着すれば、メンバー間で声がかけやすくなるので、互いに協力しながら業務を円滑に進められます。
そこで、「情報共有ツール」を導入すれば、部署間の情報共有がよりスムーズになります。ただし、操作方法が複雑だと使いこなせない社員が出てきてしまい、かえって他部署との連携が阻害される恐れがあるので、「必要な機能に過不足のないシンプルなツール」を導入しましょう。
結論、他部署との連携を強化するには、「フォルダ」で他部署との情報共有をしながら円滑なコミュニケーションを築ける、シンプルな情報共有ツールの「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事」には「コメント機能」があるため、話題が混じることなく気軽にコミュニケーションを取ることができます。また、業務情報は部署ごとに「フォルダ」で整理して管理できるため、部署の多い大企業でも情報が錯綜しません。
簡単に社内情報を共有・管理できるツール「ナレカン」

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール
ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。
「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。
自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。
また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。
更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。
- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。
<ナレカンの料金>
- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
https://www.narekan.info/pricing/
詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
他部署との連携強化に成功した事例3選
ここでは、他部署との連携強化に成功した事例3選について解説します。以下の事例を参考にして、自社の取り組みに役立てましょう。
事例1|株式会社オープンストリーム

株式会社オープンストリームでは、合併により社員数が増加し、社員同士が顔と名前認識できない課題がありました。また、プロジェクトによって頻繁にメンバーが入れ替わるため、プロジェクト開始前に互いを理解できる環境をつくる必要がありました。
そこで、情報共有ツールを導入し、社員がプロフィールを記載し、相手のバックボーンを知りやすい仕組みを整えました。さらに、トップや管理職が定期的に自身の考えを配信できる場をつくったのです。
その結果、メンバー同士で声がかけやすくなり、コミュニケーションの機会が増加して横のつながりが強化されました。また、イベントや部会時の写真・動画を投稿するなかで、情報を記録・蓄積・共有する意識が高まりました。
事例2|株式会社フルスピード

株式会社フルスピードでは、情報の蓄積・共有ができない課題がありました。そのため、「ナレッジサイト」や「ナレッジの共有ルール」がうまく運営できず、ナレッジ管理が浸透していなかったのです。
そこで、情報共有ツールを導入して、メモや質問を共有できる仕組みをつくりました。また、勉強会を実施して、共有した内容を振り返るようにしました。
その結果、他部署の業務状況を把握できるようになり、部署間のナレッジ共有が実現しました。
事例3|株式会社ミナジン

株式会社ミナジンでは、全国に新部門が立ち上がるなかで、互いの業務が把握しづらく連携が難しい課題がありました。また、仕事の成果を「フィードバックする」「社員同士で共有・称賛する」文化がなく、仕事に関するコミュニケーションが不足していました。
そこで、ピアボーナス(社員同士で報酬を贈り合う制度)ツールを導入して、仕事の成果を主体的に共有できる仕組みをつくりました。そして、拠点・部門が異なるメンバー同士でも称賛し合える体制を整えたのです。
その結果、「成果に対する承認」「部署間での協力」「事業やサービスへの誇り」に関するエンゲージメントスコア(会社への思い入れを数値化したもの)が高まりました。さらに、互いに認め合う組織風土が形成され、部門を超えたメンバー同士がクロスセル推進に取り組むようになりました。
他部署との連携を強化するメリット・成功事例まとめ
これまで、他部署との連携を強化するメリットやコツ・成功事例を中心にご紹介しました。
他部署との連携を強化すると、「業務の円滑化」や「職場への定着率向上」が可能です。ただし、仕事の目的を理解していなかったり、他部署に対する「業務への理解」や「コミュニケーション」が不足していると、部署間の連携は失敗してしまいます。
そのため、他部署の業務状況やナレッジを把握できる情報共有の仕組みをつくらなければなりません。そこで、「情報共有ツール」を導入すれば、部署間の情報共有を促進して、連携しながら業務に取り組めるのです。
したがって、他部署との連携強化には、円滑なコミュニケーションと効率的な情報共有の仕組みを構築できるシンプルなツール「ナレカン」が最適です。
ぜひ「ナレカン」を導入し、他部署との連携強化に取り組みましょう。