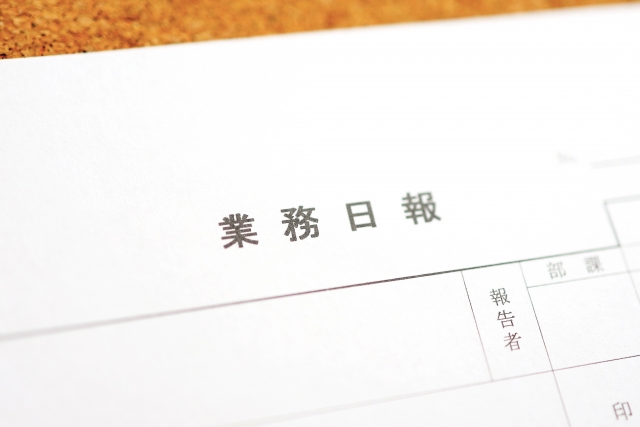近年、多くの企業でWeb形式の社内報が発行されています。そのため、作成から共有までの過程を効率化し、社内報の運用負担を軽減する目的で「アプリ」を活用する企業も増えているのです。
しかし、「Web社内報アプリの選び方が分からない」「社内報にコストはかけたくないが、使いやすい無料アプリが見つからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、おすすめのWeb社内報アプリ7選を中心にご紹介します。
- Web社内報のメリット、デメリットを知りたい
- Web社内報アプリの選定ポイントを押さえて、アプリ選びを成功させたい
- Web社内報を導入して、円滑に情報共有できるようにしたい
という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なWeb社内報アプリが分かり、スムーズな情報共有ができるようになります。
目次
Web社内報とは
Web社内報とは、情報共有アプリや電子掲示板を使い、紙の社内報をデジタル化したものを指します。以下では、Web社内報の種類とメリットを解説します。
Web社内報の種類
Web社内報アプリには、以下の3種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 情報共有アプリ型 |
・社内報を含めた社内のあらゆる情報を一元管理します。
・ただし、”多機能で一定以上のITリテラシーが求められるアプリ”もあるので注意です。 |
| 社内報特化型 |
・記事作成に役立つ機能が豊富に搭載されています。
・一方、チームでのコミュニケーションを活性化したい場合は不向きです。 |
| 社内ポータル型 |
・社内専用の情報サイトで、社内報だけでなくマニュアルや社内規定なども管理します。
・ただし、社内用のサイトを最初から構築するため、多額の初期費用がかかるケースもあります。 |
上記のように、アプリによって長所・短所は異なるので、選定するときは「自社の課題を解決できるか」を確かめましょう。
Web社内報のメリット
Web社内報には、主に以下のメリットがあります。
- 社内報をスムーズに作成・共有できる
- 社員からのフィードバックを得やすい
- 時間や場所を問わずに閲覧できる
Web社内報に備わる「テンプレート」を活用すれば、デザインを一から考える必要がありません。また、作成した社内報は印刷することなく当日中に共有できるので、伝達のタイムラグも防げるのです。
Web社内報は記事ごとにリアクションやコメントができます。そのため、記事に対する反応が一目で分かり、改善もしやすくなります。
Web社内報であればPCやスマホなどのデバイスがあれば、時間や場所を問わずに記事へアクセスできます。その結果、記事の閲覧率も上げられるのです。
このように、Web社内報を活用することで社内報の運用負担が減り、記事が読まれやすくなる仕組みを作れます。
【比較】紙社内報とWeb社内報の違い
紙社内報とWeb社内報の違いは以下の通りです。
| 紙社内報 | Web社内報 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
このように、紙の社内報とWeb社内報にはそれぞれメリット・デメリットがあります。ただし、「簡単に作成したい」「素早く社内共有したい」場合、社内報はWeb形式での運用がおすすめです。
Web社内報アプリの選定ポイント3選
ここでは、Web社内報アプリの選定ポイントを3つ解説します。以下のポイントを押さえて、社内に浸透するアプリを選びましょう。
(1)マルチデバイスに対応していること
ひとつ目のポイントは、PCだけでなく、スマホやタブレットなどのモバイル端末にも対応していることです。
モバイル端末にも対応していれば、営業先や移動中でも簡単に社内報を確認・共有できます。そのため、社員へ緊急の連絡が必要になった場合も、全社員へ周知される可能性が高くなるのです。
したがって、時間や場所を問わず社内報が見られるように、マルチデバイス対応のアプリを選びましょう。
(2)セキュリティが充実していること
2つ目のポイントは、セキュリティが充実していることです。
社内報は全社的に情報発信するので、第三者や社外への情報漏えいリスクを考慮しなければなりません。したがって、機密情報の取り扱いにはより一層注意しつつ、アクセス権限機能や2段階認証機能などのあるアプリを活用しましょう。
とくに、国際水準のセキュリティ資格「ISO27001」を取得しているアプリであれば、情報漏えいのリスクを大幅に軽減できます。
(3)誰でも簡単に使えること
3つ目のポイントは、誰でも簡単に使いこなせることです。
多機能で複雑なアプリを導入すると、ITに詳しくない従業員が使いこなせず、社内報の閲覧や共有を放置してしまう恐れがあります。したがって、全社での情報共有を確実にするには「誰でも直感的に使えるアプリ」を選ぶべきです。
たとえば、非IT企業の65歳の方でも、即日で使いこなせるほど簡単な「Stock」のようなアプリを利用しましょう。
無料あり|おすすめのWeb社内報アプリ7選
以下では、おすすめのWeb社内報アプリ7選をご紹介します。
Web社内報アプリを選ぶときの注意点は「多機能なアプリを避けること」です。機能が豊富すぎるアプリは、すべての機能を使いこなせずに費用対効果が小さくなったり、操作が難しく社内に浸透しなかったりするデメリットがあります。
そこで、Web社内報に必要な「記事を蓄積・共有する機能」「記事にコメントする機能」「記事を分かりやすく管理する機能」の3つが過不足なく備わったアプリを選びましょう。さらに、直感的に操作できるアプリを選ぶと”社内に定着しない事態”を防げます。
結論、自社に最適なWeb社内報アプリは、必要な機能に過不足がなく、非IT企業の65歳の方でも使いこなせるほどシンプルな「Stock」一択です。
Stockの「ノート」で作成・共有した記事は、内容や部署ごとに「フォルダ」で振り分けられるので、欲しい情報がすぐに見つかります。また、ノートに紐づく「メッセージ」で気軽にコメントできるため、社内コミュニケーションも活性化されるのです。
【Stock】Web社内報を最も簡単に運用できるアプリ

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
【WEB MEDIA Z(WMZ)】コミュニケーション不足を解消するアプリ

<WEB MEDIA Z(WMZ)の特徴>
- 公開日時を設定できる
- シンプルな操作性
事前に記事を作成し、公開日時を設定する機能が搭載されています。すきま時間を使って作業を進められるため、編集の負担が軽減されます。
直感的なボタンで記事の作成・編集ができるため、ITに詳しくないチームでも比較的使いやすいです。
<WEB MEDIA Zの機能・使用感>
- アクションログ機能
- 通知機能
ページの閲覧数やいいね数、コメント数などを数値として記録できるので、あとからPDCAを回しやすくなるメリットがあります。
記事へのコメントや返信は逐一メールで通知されるため、重要なメッセージを見落とすリスクも軽減できます。
<WEB MEDIA Z(WMZ)の注意点>
- 導入までに時間がかかるケースもある
導入時期は、自社で導入しているシステムの状況をヒアリングしたうえで決まります。したがって、導入までに工数がかかる場合もあるので注意が必要です。
<WEB MEDIA Z(WMZ)の料金体系>
- 要問い合わせ
【SOLANOWA】豊富な機能を持つWeb社内報アプリ

<SOLANOWAの特徴>
- 多彩な情報を掲載できる
- 高度なセキュリティ
文章や写真だけでなく、YouTube動画を紐づけるなど動画や音声ファイルも掲載できます。そのため、伝えられる情報の幅が広いことが特徴です。
総務省が定める指針に沿って、不正プログラム対策やIPアドレス制限など、情報を安全に守れるセキュリティ対策を行っています。
<SOLANOWAの機能・使用感>
- コメント機能
- グループ別閲覧制限機能
記事別にコメントを付けられるため、フィードバックを得たい場合に役立ちます。また、コメントは「ON/OFF」に切り替えられる点も便利です。
部署や役職といった任意のグループ別に閲覧制限を設けられるので、大切な情報が意図せず外部に漏れるのを防げます。
<SOLANOWAの注意点>
- サポート体制が弱い
- 文字の融通が利きにくい
不便な点をリクエストしても、対応が遅いという点でサポート体制の弱さを感じるユーザーもいます。(参考:ITreview)
「文字の色味を調整ができない」といった意見がありました。(参考:ITreview)
<SOLANOWAの料金体系>
- 要問い合わせ
【TUNAG】社内の交流を促進するアプリ

<TUNAGの特徴>
- 情報がリアルタイムで届く
- 充実したカスタマイズ機能
社内報の投稿が流れてくるタイムライン機能が搭載されています。重要な投稿は「プッシュ通知」や「必読マーク」で周知できます。
組織の規模や目的に合わせて、機能を自由にカスタマイズできます。そのため、大規模チームでも導入しやすいです。
<TUNAGの機能・使用感>
- プロフィール機能
- チャット機能
社員一人ひとりが顔や名前、趣味などを登録できるプロフィール機能が搭載されており、気軽なコミュニケーションのきっかけになります。
チャット機能では、テキストだけでなく画像や動画もやりとりできます。そのため、「社内報の管理だけでなく、コミュニケーションも効率化したい場合」に有効です。
<TUNAGの注意点>
- リアクション機能が限られる
- 更新が遅い
既読機能はあるものの「いいね」のようなリアクション機能はありません。それゆえ、細かなリアクションを示したいユーザーからは改善要望もあります。(参考:ITreview)
アプリを立ち上げるときにチャットがフリーズしてしまうなど、更新が遅いように感じるというユーザーの意見もありました。(参考:ITreview)
<TUNAGの料金体系>
参考:TUNAGの料金ページ
- 初期費用+月額費用(要問い合わせ)
【社内報アプリ】社内ポータルとして使えるアプリ

<社内報アプリの特徴>
- 総合情報ポータル
- マルチデバイス対応
社内報の記事だけでなく、各種資料や動画、問い合わせ窓口など、あらゆる情報を集約した情報ポータルとして使えます。
PCだけでなくスマホからも社内報を見られるため、外回りの多い営業担当や、一人ひとりにPCが与えられない職場でも便利です。
<社内報アプリの機能・使用感>
- 未読一覧機能
- 記事のグループ分け機能
ユーザーが読んでいない記事を一覧で表示する機能が搭載されており、社内報の見逃しを防げるメリットがあります。
部署や役職に応じてユーザーをグループ分けし、閲覧可能な記事のみを設定できます。その結果、ユーザーは各々に最適な記事を見られるので「誰からも読まれない記事」を減らせるのです。
<社内報アプリの注意点>
- 円滑なコミュニケーションをするには不向き
社内SNSのような「コメントへのメンション機能」はありません。そのため、チームで円滑なコミュニケーションをとりたい場合は別のアプリを検討しましょう。(参考:社内報アプリ|よくあるご質問)
<社内報アプリの料金体系>
参考:社内報アプリの料金ページ
- 初期費用+月額費用(要問い合わせ)
【ourly】分析機能に特徴があるweb社内報アプリ

<ourlyの特徴>
- シンプルな設計
- 国際水準のセキュリティ
ITが苦手な人でも使いやすいシンプルな設計なので、サイトの設定や記事作成もスムーズにできます。
国際水準のセキュリティ資格である「ISO27001」を取得しており、高い安全性を確保しています。
<ourlyの機能・使用感>
- 独自の分析機能
- コミュニケーション機能
記事の閲覧数や読了率、リアクション率など独自の指標が分析されるため、その後の改善活動に活用できます。
記事ごとにリアクションやコメントを通してコミュニケーションをとれるので、社内SNSとしての役割も果たします。
<ourlyの注意点>
- 人数に応じて料金が変更する
人数に応じて料金が左右するので、費用の詳細を知りたい場合は入力フォームより確認しましょう。
<ourlyの料金体系>
参考:ourlyの料金ページ
- 初期導入費用+月額費用
【NotePM】ナレッジ共有に特化したアプリ

<NotePMの特徴>
- 豊富な機能が備わっている
- 欲しい情報がすぐに見つかる
記事作成はもちろん、レポート機能やコメント機能、外部サービスとの連携機能など、豊富な機能が備わっています。
フォルダ単位での階層管理に加えて、ファイルの中身も全文検索できる「検索機能」があるので、目的の情報へすぐにたどり着けます。
<NotePMの機能・使用感>
- 閲覧履歴の表示
- アクセス制限機能
ページを見た人とその時間の履歴が残るため、社内報を全社員が読んでいるかを確認できます。
社内報の公開範囲を自由に設定できるので、外部に知られたくない情報がある場合に効果的です。
<NotePMの注意点>
- ファイルの一括ダウンロードはできない
- 直感的な操作はしにくい
一部のユーザーからは「添付ファイルを一括ダウンロードできれば、ドキュメントの見直しがしやすい」との声もあります。(参考:ITreview)
事前のIT知識を持った人以外にとっては、操作がしにくいといった意見が一部見られました。(参考:ITreview)
<NotePMの料金体系>
以下は各料金プランの比較表です。(左右にスクロール可)
参考:NotePMの料金ページ
| プラン8 | プラン15 | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 |
4,800円/月 |
9,000円/月 |
15,000円/月 |
30,000円/月 |
60,000円/月 |
120,000円~/月 |
| 上限人数 |
8人まで |
15人まで |
25人まで |
50人まで |
100人まで |
200人まで |
| ストレージ容量 |
80GB |
150GB |
250GB |
500GB |
1TB |
2TB |
<比較表>おすすめのWeb社内報アプリ一覧
以下は、おすすめのWeb社内報アプリ7選の比較表です。(左右にスクロール可)
| Stock【一番おすすめ】 | WEB MEDIA Z | SOLANOWA | TUNAG | 社内報アプリ | ourly | NotePM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
誰でもシンプルに使えるほど簡単 |
コミュニケーション不足を解消できる |
豊富な機能を持つ |
社内の交流を促進する |
社内ポータルとして使える |
分析機能を搭載 |
ナレッジ共有に特化 |
| 注意点 |
記事作成機能やデータ分析機能はない |
チームによっては導入に時間がかかる |
ヘルプサイトから目的の記事を探しづらい |
「いいね」などのリアクション機能はない |
コメントへのメンションはできない |
アップデート後に起動しないことがある |
添付ファイルは一括ダウンロードできない |
| 料金 |
・無料
・有料プランでも500円~/ユーザー/月 |
・無料プランなし
・詳細は要問い合わせ |
・無料プランなし
・詳細は要問い合わせ |
・無料プランなし
・詳細は要問い合わせ |
・無料プランなし
・詳細は要問い合わせ |
・無料プランなし
・詳細は要問い合わせ |
・無料プランなし
・有料プランは4,800円~/月 |
| 公式サイト |
「Stock」の詳細はこちら |
「WEB MEDIA Z」の詳細はこちら |
「SOLANOWA」の詳細はこちら |
「TUNAG」の詳細はこちら |
「社内報アプリ」の詳細はこちら |
「ourly」の詳細はこちら |
「NotePM」の詳細はこちら |
このように、アプリによって特徴は異なるので、表を参考にしながら自社の目的に適したものを選びましょう。
Web社内報の制作方法!かかる費用は?
制作手段としては、現在使用中の情報共有ツールを使って作るまたはWeb社内報アプリを新たに導入して作るの2パターンあります。
かかる費用は、現在使用中の情報共有ツールを使う場合、既存のツールを活用するため追加費用が発生せず、料金を安く抑えることができます。一方で、新たにWeb社内報専用アプリを導入する場合は初期費用と月額費用が新たにかかります。
一方で、「Stock」のように社内報をはじめとした、あらゆる社内情報の共有に役立つアプリを導入すれば、ひとつのツールで完結するので結果として料金が安価になるのです。
おすすめのWeb社内報アプリや選定ポイントまとめ
ここまで、おすすめのWeb社内報アプリ7選や、選定ポイントを中心に解説しました。
Web社内報は大きく3種類に分けられますが、社内報のための機能が豊富に搭載された「社内報特化型」は費用対効果が小さくなるリスクがあり、社内情報をまとめられる「社内ポータル型」は初期費用がかさんでしまいます。
したがって、社内報に必要な機能を過不足なく備えており、初期費用がかからないことが多い「情報共有型アプリ」を導入しましょう。さらに、誰でも直感的に利用できるアプリであれば、ITが苦手なチームでもすぐに浸透します。
結論、Web社内報の運用には、ITに詳しくない65歳の方でも、簡単に使えるアプリ「Stock」が最適なのです。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入し、社内報の作成・共有・管理を効率化しましょう。