今日では、多くの医療機関でカルテの電子化が浸透しています。カルテを電子化すれば、紙のカルテで行っていた作業が削減できたり、カルテ管理の煩雑さも解消されたりする効率化が図れるのです。
一方、なかにはカルテの電子化に不安があり、紙のままカルテを取り扱っている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、カルテの電子化によるメリットや注意点を中心にご紹介します。
- 紙でのカルテ管理に非効率さを感じているものの、電子化への移行に不安がある
- カルテを電子化するにあたって押さえるべきポイントを把握したい
- 電子化によって、カルテの作成だけでなく管理の煩雑さも解消したい
という方はこの記事を参考にすると、カルテの電子化によるメリットや注意すべき点がわかり、カルテの作成・管理におけるストレスを解消できるようになります。
目次
電子カルテとは
電子カルテとは、患者の情報が記載されたカルテを電子化したものです。
患者の症状だけではなく、治療経過や処方箋情報などの履歴情報を随時更新し、最適な治療法を採るために活用されています。
現在は、医療機関などでカルテのクラウド化が進み、電子カルテの普及率が高くなっているのです。
カルテを電子化すべき理由とは
カルテを電子化すべきなのは、紙でカルテを取り扱うよりも情報連携のスピードアップを図れるほか、メンバーの負担やカルテ管理の煩雑さも改善できるためです。
また、厚生労働省が発表している「電子カルテシステム等の普及状況の推移」を見ると、電子カルテを扱っている一般病院は、平成20年から令和2年までの間に約4倍に増えているのがわかります。
したがって、カルテの電子化は今日におけるトレンドとなっているうえ、チーム間での情報やりとりを円滑化するのに不可欠なプロセスと言えるのです。
カルテの電子化によるメリット
ここでは、カルテの電子化によるメリットを4つご紹介します。チーム全体にカルテの電子化を浸透させるためにも、必ず把握・共有しましょう。
記載時間を短縮できる
カルテを電子化するメリットとしてまず挙げられるのが、記載時間を短縮できる点です。
たとえば、カルテに記載ミスがあった場合、紙のカルテであれば修正に時間がかかったり、再度新しいカルテを印刷したりしなくてはなりません。しかし、電子化すれば記載ミスも数クリックで修正可能なことから、記載時間の短縮が可能になるのです。
このように、電子化により記載時の負担が大幅に軽減されて、カルテを迅速に記載できるようになります。さらに、印刷による時間的コストがかかる心配もありません。
時間・場所を問わずにアクセスできる
時間・場所を問わずにアクセス可能なのも、カルテの電子化によるメリットです。
紙のカルテであれば現場に出勤したり、メールや電話をしたりしなければカルテの内容を共有できません。しかし、電子カルテはPCやスマホ、タブレットとのデバイスを問わず確認できるため、時間や場所に関わらず情報へのアクセスが可能になります。
このように、カルテを電子化すれば、現場にいない場合でもリアルタイムでカルテの内容がわかるので、カルテを共有するのにメールや電話をする必要もなくなるのです。
紛失リスクが軽減できる
紛失リスクが軽減できるのもカルテを電子化するメリットです。
カルテを紙で管理している場合、ほかの資料と混ざっても一目でわかりにくいので、カルテの紛失にも繋がりかねません。もしカルテが紛失してしまうと、最悪の場合、患者やメンバーの個人情報が漏洩する恐れもあります。
しかし、カルテを電子化すると、患者や部署ごとにカルテのファイルを明確に分けられるため、紛失リスクを削減可能なのです。
必要な情報をスムーズに検索できる
必要な情報をスムーズに検索できるメリットもあります。
紙でのカルテ管理は属人的になりやすく「必要なカルテの管理場所がわからない」事態も起こり得ます。しかし、カルテを電子化して管理すれば、キーワードやファイル名での検索ができるので、目的のカルテを探す時間もかからなくなるのです。
このように、情報検索の時間を短縮して、目的のカルテをスムーズに取り出せるようにするためにも、紙でのカルテ管理をしている場合は早急に電子化へ移行しましょう。
カルテの電子化によるデメリット
以下は、カルテの電子化によるデメリットをふたつ紹介します。デメリットをチーム全体で把握して、電子カルテ導入・運用時の対策をあらかじめ検討しておくことが大切です。
導入・運用にコストがかかる
導入時だけでなく運用時にもコストがかかります。
導入時の費用はもちろん、導入にメンバーが慣れるための教育コストも考慮しなければなりません。また、電子化に活用するITツールは月々の料金が発生するので、継続的に運用できる運用コストも必要です。
したがって、チームのITリテラシーにマッチした操作性・料金体系のITツールを活用することが必須になります。
情報漏洩のリスクがある
ITツールで患者情報を一元管理するので、セキュリティが強固でなければ情報漏洩のリスクがあります。
ITツールでカルテを電子化してもルールが整備されていなければ、情報が外部に持ち出されたり、外部から攻撃を受けたりする可能性が高まるのです。したがって、カルテを電子化するときは「ISO27001(ISMS)の取得」がある、セキュリティの強固さを備えたITツールを導入しましょう。
また、直感的に操作できないツールでは、誤操作による情報漏洩のリスクもあるので注意が必要です。
カルテを電子化する際の注意点
ここでは、カルテを電子化する際の注意点を3つご紹介します。カルテの電子化によるトラブルを避けるためにも、確実に押さえましょう。
事前に運用ルールを設ける
カルテを電子化する際にまず注意すべきなのが、事前に運用ルールを設ける点です。
カルテを電子化したとしても、「作成や管理の方法がメンバーによって異なる」状態では電子化したデータが散乱し、紙でのカルテ管理と変わりません。また、メンバー各自のやり方でカルテが扱われれば、ノウハウの蓄積・共有も困難になってしまうのです。
このような事態を防ぐためにも、管理方法の統一を義務づけたり、テンプレートを用意したりといった運用ルールをあらかじめ設けておきましょう。
セキュリティを強固にする
セキュリティを強固にするのも、カルテを電子化するうえで欠かせない点です。
セキュリティが脆弱な電子カルテには、コンピュータウイルスによるカルテのデータ破損や不正アクセスの危険性があります。仮にカルテのデータが破損したり不正アクセスが発生したりした場合、データの修復が不可能となり情報漏洩の危険性も高くなるのです。
このような事態を防ぐためにも、カルテを電子化する際は必ずウイルス対策ソフトを導入したり、強固なセキュリティを持つツールを活用したりする対策をとりましょう。
使い方が簡単なツールを活用する
電子化したカルテの管理には、使い方が簡単なツールを活用する点にも注意が必要です。
ツールの操作が複雑であれば、ITに不慣れなメンバーの理解が及ばず、最悪の場合ツールの運用ができなくなる恐れもあります。また、ツールの運用にあたって、教育コストも無駄にかかってしまうのです。
そのため、電子化したカルテは、必ず使い方が簡単なツール上で管理しましょう。たとえば、「Stock」のようなツールを使うと、誰でもストレスなくカルテ管理が行えます。
電子化したカルテの管理に最適なツール
ここからは、電子化したカルテの管理に最適なツールをご紹介します。
カルテを電子化すれば、作業負担の軽減やアクセス性の向上、情報検索の円滑化といった大きなメリットが得られます。また、電子化したカルテを効率的に管理するには、チーム全体で活発な情報共有が可能な「クラウドツール」の導入・運用一択になるのです。
ただし、カルテの「管理」のみに重点を置くあまり、カルテごとに更新される情報が適切に管理できなければ意味がありません。煩雑な状態を放置すれば「古い情報をそのまま扱っていた」のような重篤なミスも発生しかねないからです。
したがって、ツールを選定時には、操作性が簡単であることはもちろん「情報が随時更新され、共有にストレスが伴わないこと」も必ず押さえましょう。そこで、誰でも簡単かつ確実にカルテの情報をストックできる情報共有ツール:「Stock」が必須です。
Stockの「ノート」にカルテの情報を蓄積すると、強固なセキュリティ下で任意のメンバーへ簡単に共有できます。また、直感的な「フォルダ」で患者や部署ごとに情報が振り分けられるため、必要なカルテの検索に時間がかかる心配もありません。
カルテの情報を最も簡単に管理・共有できるツール「Stock」
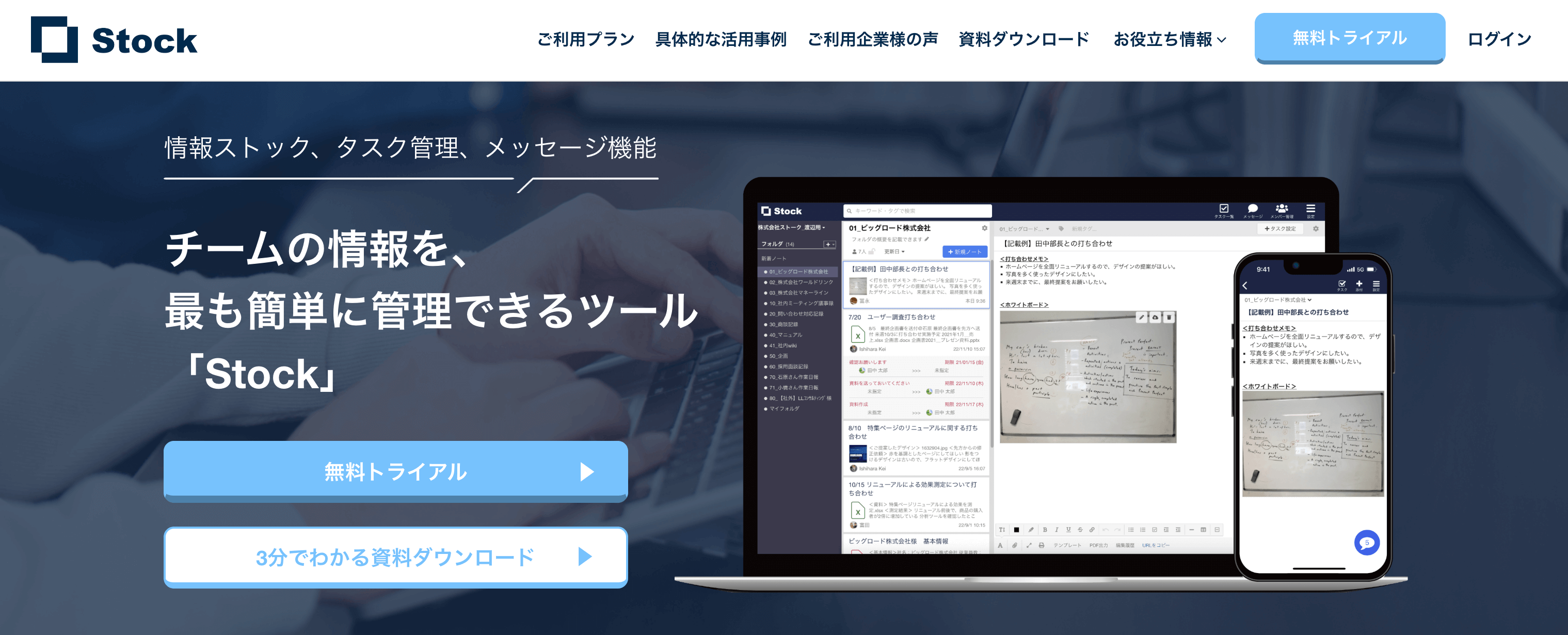
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
※最低ご利用人数:5ユーザーから
カルテの電子化によるメリットや注意点まとめ
これまで、カルテの電子化によるメリットや注意点を中心にご紹介しました。
カルテを電子化すれば、紙のカルテでの作業負担や管理の煩雑さを解消できます。また、電子化したカルテを効率的に管理するためには、チーム全体での情報共有が可能な「クラウドツール」を活用しましょう。
一方、日々更新されるカルテの情報を確実に蓄積できなかったり、ツールの操作性が複雑だったりすればメンバーの抵抗感を生んでしまいます。そのため、「簡単な操作性、かつカルテの情報を適切に管理できるツール」を選定すべきなのです。
そこで、Stockのように、非IT企業の65歳以上の社員でも即日で使いこなせるほどシンプルなツールを使えば、電子カルテの管理を効率化できる機能が過不足なく搭載されているので、管理にストレスが発生しません。
ぜひ「Stock」を導入し電子化したカルテをストレスなく、かつ確実に管理できる環境を実現しましょう。




