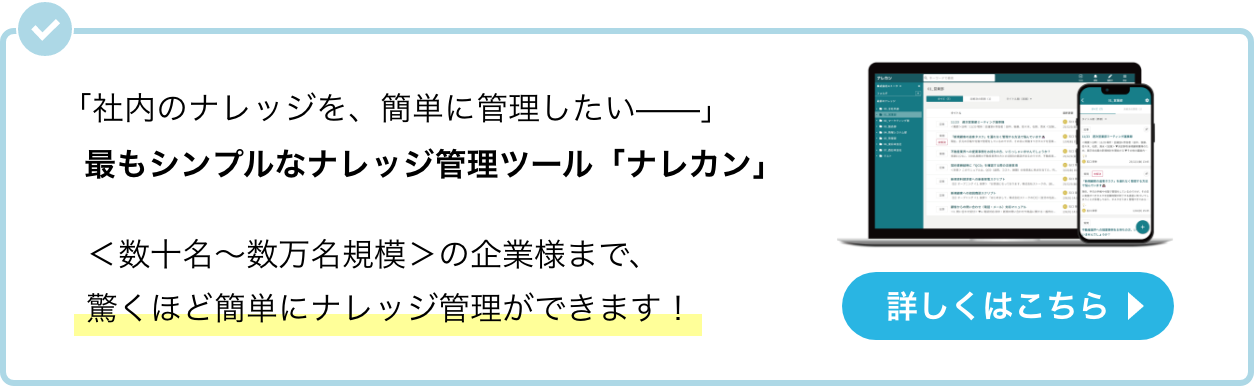マニュアルは社内業務を円滑に進めるうえで欠かせません。したがって、作成して終わりではなく、関係者全体へ共有して、定着化させる仕組みづくりが求められます。
しかし、「マニュアル管理の重要性は把握しているが、適切に管理ができず活用されない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マニュアル運用の手順やマニュアルを管理・共有できるツール7選を中心にご紹介します。
- マニュアルが煩雑化しており、社内で活用されず困っている
- 複数あるツールの中でどれがマニュアル管理に最適かわからない
- ツールを活用してマニュアルの作成から管理まで一貫したい
という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なマニュアル管理ツールが分かり、マニュアルはもちろんあらゆる社内情報を誰もが管理できるようになります。
目次
マニュアル管理の必要性とは
マニュアル管理は、マニュアルを正しく使えるようにするうえで重要です。
マニュアルを作成することで、業務内容の属人化を防止したり、作業時間を短縮したりするメリットがあります。しかし、管理が行き届かず「記載されている情報が古い」「保存場所が分からない」といった事態では、マニュアルは放置されてしまうのです。
以上のように、効率的な業務遂行を実現するには、マニュアルを作成するだけでなく、管理も重要なのです。
社内マニュアルの効果的な管理・活用方法とは
社内マニュアルを効果的に管理・活用する方法はマニュアル管理ツールを使うこと一択です。
マニュアル管理ツールを使えば、PCに加えてスマホからでもアクセス可能なので、時間や場所を問わず資料を閲覧できるようになります。また、紙と違って簡単に整理できるため「マニュアルの保存場所が分からず活用されない」事態が起こりません。
したがって、マニュアルを効率よく運用するには、必要な資料が見つけやすくなる「マニュアル管理ツール」を導入しましょう。
マニュアル運用の手順
以下では、マニュアルを運用するための手順を説明します。3つのポイントを押さえてマニュアルを効率よく活用しましょう。
(1)分かりやすい文書を作成する
はじめに、どのような業務に関するマニュアルを作成するのかを決定します。
関係者にインタビューや調査などを実施し、必要な情報を収集して、マニュアルの内容を詳細に書き起こします。また、文書を作成するときは、現場の人が忙しくてもすぐに理解できる表現を心掛けましょう。
また、テキストだけでマニュアルを作成しても、文章量に圧倒されるので、活用されにくくなります。したがって、図や画像など、視覚的要素を入れることもおすすめです。
(2)従業員へ共有する
次に、マニュアルを適切な媒体で共有しましょう。
紙媒体でマニュアルを共有する方法よりも、ツールやアプリを導入した方がマニュアルを複数の社員に同時共有できます。また、必要な従業員にマニュアルへのアクセス権限を正しく付与すれば、情報漏えいも発生しません。
とくに、マニュアルをはじめとした「何度も見返す情報」には、誰でも簡単にたどり着けなければ不便です。そこで、シンプルな情報構造に加えて、高度な検索機能が備わった「ナレカン」のようなツールを利用する企業が増えています。
(3)内容を更新する
最後に、マニュアルは共有するだけでなく内容の更新が欠かせません。
なぜなら、更新を怠ると古いマニュアルを参照して業務ミスにつながったり、形骸化して誰も活用しないマニュアルになってしまったりするからです。たとえば、更新が抜けたまま放置していると他の社員が誤ったまま業務を進めるトラブルにもつながりかねません。
したがって、マニュアルは内容を定期的に見直し、常に最新情報が得られる状態にしておく必要があるのです。
社内マニュアルの管理・共有がうまくいかない原因
以下では、社内マニュアルの管理がうまくいかない原因を2つご紹介します。効果的なマニュアル管理を実現したい方は必見です。
(1)検索性が悪い
1つ目の原因は「検索性が悪い」ことです。
管理ツールの検索性が悪いと、社員は目的の情報をスムーズに見つけられません。その結果、探すのが面倒となりマニュアル自体が閲覧されなくなってしまいます。
そのため、「タイトル」や「ファイル名」で絞り込みできる検索機能が搭載された管理ツールを導入しましょう。さらに、添付されたファイル内まで検索が行き届く高度な検索機能があれば、欲しい情報へすぐにたどりつけるのです。
(2)テーマごとに分類できていない
2つ目の原因は「テーマごとに分類できていない」ことです。
正しく分類ができていないと、どこに何の情報があるのか分からなくなり、必要なマニュアルを探すのに手間と時間がかかってしまいます。そのため、章・節・項などを決めて重要度や順序を示すことが大切なのです。
そこで、「ナレカン」のように自由にフォルダの階層を分けて管理できるツールであれば、目的のマニュアルにアクセスしやすくなるのです。
【必見】おすすめのマニュアル管理・共有ツール7選
以下では、おすすめのマニュアル管理・共有ツール7選をご紹介します。
マニュアル管理ツールであれば、単純にマニュアルを作成できるだけでなく、管理・共有までひとつのツール上で完結できます。そのため、紙の資料やExcelよりも管理が簡単なうえ、必要に応じて情報の更新も素早くできます。
ただし、社員が時間や場所を問わずマニュアルを確認するには「共有のしやすさ」や「アクセス性の良さ」が揃ったツールであることが前提です。加えて、大企業の場合、従業員によってITリテラシーに差があるので「全社員が直感的に使えるか」を重視しましょう。
結論、マニュアルの管理には、マルチデバイスに対応しており、メールを使える方ならば、すぐに使える程シンプルな「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事」では、画像を取り入れたマニュアルを作成でき、「フォルダ」で案件ごとに振り分けも簡単です。また、ほかの人に手順を確認したいときは、知恵袋のような形式の「質問」を投稿すれば、質問内容と回答を全員で共有でき、認識を統一できます。
【ナレカン】マニュアルの不明点が質問しやすいツール

「ナレカン」|最もシンプルなナレッジ管理ツール
ナレカンは、最もシンプルなナレッジ管理ツールです。
「数十名~数万名規模」の企業様のナレッジ管理に最適なツールとなっています。
自分でナレッジを記載する場合には「記事」を作成でき、『知恵袋』のような感覚で、とにかくシンプルに社内メンバーに「質問」することもできます。
また、ナレカンを使えば、社内のあらゆるナレッジを一元的に管理できます。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積することが可能です。
更に、ナレカンの非常に大きな魅力に、圧倒的な「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」があります。ナレカン導入担当者の方の手を、最大限煩わせることのないサポートが提供されています。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【機能】 「ナレッジ管理」に特化した、これ以上なくシンプルなツール。
「フォルダ形式」で簡単に情報を整理でき、「記事形式」「(知恵袋のような)質問形式」でナレッジを記載するだけです。
- 【対象】 数十名~数万名規模の企業様で、社内のあらゆるナレッジを一元管理。
「マニュアル」 「社内FAQ」「議事録」「トークスクリプト」等、あらゆるナレッジを蓄積可能です。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
圧倒的なクオリティのサポートもナレカンの非常に大きな魅力です。貴社担当者様のお手間を最大限煩わせることないよう、サポートします。
<ナレカンの料金>
- ビジネスプラン :標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン :管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
https://www.narekan.info/pricing/
詳しい金額は、下記「ナレカンの資料をダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
【Stock】最も簡単にマニュアルを管理・共有できるツール
「Stock」はシンプルな操作性が特徴で、誰でも直観的にマニュアルを作成・管理できるツールです。
Stockの「ノート」に作成したマニュアルは「フォルダ」で案件ごとに振り分けることができます。また、ノートに紐づく「メッセージ」によって、マニュアルごとに話題が混ざらず、更新内容もメンバーへ簡単に伝えられます。

「Stock」|最もシンプルな情報ストックツール
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できるツールです。「社内の情報を、簡単にストックする方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
<Stockをおすすめするポイント>
- ITに詳しくない数人~数千人の企業向け
ITの専門知識がなくても問題なく、あらゆる企業が簡単に始められます。
- とにかくシンプルで、誰でも使える
余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残せます。
- 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、さらに直感的な「タスク管理」も可能です。
<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

加井 夕子 さん、海野 紘子 さん
SBIビジネス・イノベーター株式会社 |
|
「SBIグループの厳格なセキュリティ基準をも満たす、誰にでもお勧めの情報ストックツールです」 ★★★★★ 5.0 当社が導入するシステムには非常に厳格なセキュリティ基準を満たすことが要求されていますが、Stockのシステムは極めて高度なセキュリティ基準で開発・運営されているため、SBIグループのセキュリティ基準でも全く問題なく導入することができました。 |

江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ(栃木SC) |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
<Stockの料金>
- フリープラン :無料
- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月
- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月
【iTutor】多機能かつマニュアル作成に特化したツール

<iTutorの特徴>
- 簡単にマニュアルを作成できる
- e-ラーニングの作成もできる
マニュアルの編集や出力が数クリックで完了するので、作成に手間がかかりません。
ドラッグ&ドロップでeラーニングを作成できるので、社内教育のツールとしても活用可能です。
<iTutorの機能・使用感>
- 操作マニュアルを作成できる
- 教育コンテンツとして活用できる
実際に操作するだけで操作内容をキャプチャ(自動録画)できるので、操作マニュアルの作成に貢献します。
マニュアルを社員教育に活用したい場面では、トレーニングコンテンツの作成が可能です。
<iTutorの注意点>
- 保守サポート契約が必須
- ヘルプが分かりづらい
iTutorの購入と同時に保守サポート契約への加入が必須となっています。
ユーザーの口コミでは「ヘルプが少しみづらいのでもう少し細かくヘルプを記載してほしいです」という声も挙がっています。(引用:ITreview)
<iTutorの料金>
- Videoエディション:380,000円~
- Documentエディション:380,000円~
- for Mac:550,000円~
- Standardエディション:700,000円~
- Proエディション:900,000円~
動画制作など、動画メインのプランです。
手順書や業務マニュアルに特化したドキュメントメインのプランです。
Macを使ってマニュアルを作成できるプランです。
ドキュメントも動画も作成したい場合のプランです。
各種Officeフォーマットへのエクスポートや画像変換ができるプランです。
【Dojo】豊富なテンプレートが選択できるツール

<Dojoの特徴>
- 簡単に高品質なマニュアルを作成できる
- 作成したeラーニングを学習管理システムで配信できる
豊富なテンプレートと自動音声合成機能を利用すれば、誰でも高品質なマニュアルを作成できます。
eラーニングの作成に対応しているほか、完成したコンテンツは学習管理システム「GAKTEん」で配信できて、作成から活用まですべての場面で活躍します。
<Dojoの機能・使用感>
- 操作説明文を自動作成できる
- 音声を自動変換できる
操作ステップを表示したい場面では、操作の種類・内容を自動で取得して、説明文を作成できます。
音声を26種類以上の言語に自動変換できるので、外国人スタッフ向けのマニュアル作成に貢献します。
<Dojoの注意点>
- 動画編集画面が複雑
- 不慣れだと使いづらい
多機能ゆえに動画編集画面が複雑なため、ITに不慣れなメンバーに活用されなくなる恐れがあります。
ユーザーの口コミでは「直感的な操作がしずらく、Dojoを利用するためのマニュアルをDojoでつくる、といった作業が必要」という声も挙がっており、ITに不慣れな方には操作が難しいです。(参考:ITreview)
<Dojoの料金>
- 要問い合わせ
【TeんDo】eラーニングにも対応しているツール

<TeんDoの特徴>
- 簡単に精度の高いマニュアルをつくれる
- 対応しているマニュアルの種類が多い
いくつかの操作だけでマニュアルが完成します。また、図表や音声の挿入もできるため自社に合ったマニュアルに仕上げられるのです。
テキストマニュアルのほか、eラーニングコンテンツなども作成できます。
<TeんDoの機能・使用感>
- PowerPointの資料を取り込める
- 動画マニュアルを作成できる
過去に作成した教材資料を活用したい場面では、PowerPointのコンテンツを取り込めます。
動的コンテンツも出力できるので、実際に動画を確認しながら正しく手順を理解したい場面に役立ちます。
<TeんDoの注意点>
- 音声合成やマニュアルエディターは基本機能外
日本語音声合成、多言語音声合成、マニュアルエディターはオプションとなっているため、利用する際には別途料金が必要になります。(引用:SaaS LOG)
<TeんDoの料金>
- ベーシックプラン:80,000円/ライセンス/月(月払い)
- オプション:16,000円/ライセンス/月(月払い)
※最低12ヶ月以上の契約が必要です。
【Teachme Biz】インストール型にも対応しているツール

<Teachme Bizの特徴>
- 必要なマニュアルがすぐに見つかる
- アクセスログ機能が搭載されている
アプリ上にすべてのマニュアルがあるため、必要な資料を見つけやすくなります。
マニュアルの活用度を測る「アクセスログ機能」によって、データに基づきながらマニュアルを浸透させられます。
<Teachme Bizの機能・使用感>
- 手順をステップ構造で表せる
- 手順の抜け漏れを防止できる
手順をステップ構造で表せるので、マニュアルのステップ化に貢献します。
1つの動画からマニュアルとして使いたい場面を画像・動画として切り出せるので、ほかのマニュアル管理ツールと比べて、情報の抜け漏れが発生しづらいです。
<Teachme Bizの注意点>
- マニュアルを探しずらい
ユーザーの口コミでは「マニュアルが増えてくると フォルダ管理だけだと限界があるので、マニュアルの目次のようなものが必要と感じている。」という声も挙がっており、素早くマニュアルを検索したい方には不向きです。(引用:ITreview)
<Teachme Bizの料金>
- スタータープラン:59,800円/~60名/月
- ベーシックプラン:119,800円/~180名/月
- エンタープライズプラン:319,800円/~600名/月
【COCOMITE】画像・動画を使ったマニュアルを作成できるツール

<COCOMITEの特徴>
- 画像・動画マニュアルを少ない工数で作成できる
- フォルダにアクセス権限を付けられる
基本レイアウトに沿うだけで画像・動画マニュアルを作成できます。
フォルダごとにアクセス権限を付けられるため、セキュリティを高められます。
<COCOMITEの機能・使用感>
- フォルダやファイルへスムーズにアクセスできる
- 複数の媒体で閲覧できる
共有リンクを取得すれば、必要なフォルダやファイルへ迅速にアクセスできるようになります。
紙への印刷も可能なので、PC・スマホ・タブレット・紙とさまざまな手段でマニュアルを閲覧したい場合に役立ちます。
<COCOMITEの注意点>
- マニュアルの作成手順が分かりづらいと感じることもある
- ITに不慣れな職場には負担が大きい
ユーザーの口コミでは「マニュアルを作成する場合の手順が分かりづらい」という声も挙がっています。(参考:ITreview)
使い方を学ぶための「勉強会」を受けることも可能ですが、1回あたり100,000円の費用が発生します。そのため、ITに不慣れな職場で運用する場合には金銭的負担が大きく、予算をオーバーしないか要検討が必要です。
<COCOMITEの料金>
パッケージプランは、以下の通りです。別途、初回登録料として65,000円かかります。
- スモールパック:408,000円/年
- トリセツパック:480,000円/年
- ミディアムプラン:792,000円/年
- ラージパック:2,784,000円/年
従量課金プランは、以下の通りです。
- エントリープラン:28,600円/月(月払い)
- スタンダードプラン:78,000円/月(月払い)
- エンタープライズプラン:286,000円/月(月払い)
【無料でも使える】おすすめのマニュアル管理・共有ツール比較表
以下は、無料でも使えるおすすめのマニュアル管理・共有ツールの比較表です。
| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | iTutor | Dojo | TeんDo | Teachme Biz | COCOMITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
マニュアルの不明点が質問しやすいツール |
最も簡単にマニュアルを管理・運用できるツール |
多機能かつマニュアル作成に特化したツール |
豊富なテンプレートが選択できるツール |
eラーニングにも対応しているツール |
インストール型にも対応しているツール |
画像・動画を使ったマニュアルを作成できるツール |
| フォルダ管理 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】 |
【×】 |
【〇】 |
【〇】 |
| メッセージ機能 |
【〇】 |
【〇】 |
【×】 |
【×】 |
【×】 |
【〇】 |
【〇】 |
| マルチデバイス対応か |
【〇】 |
【〇】 |
【×】 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】 |
【〇】 |
| 注意点 |
フォルダの階層が深くなりすぎないように工夫が必要 |
操作内容をキャプチャ(自動録画)する機能はない |
保守サポート契約が必須 |
動画編集画面が複雑 |
音声合成やマニュアルエディターは基本機能外 |
検索性が低い |
マニュアルの作成手順が分かりづらいと感じることもある |
| 料金 |
・無料プランなし
・有料プランは資料をダウンロードして確認 |
・無料
・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |
・無料プランなし
・有料プランは380,000円~ |
・要問い合わせ |
・無料プランなし
・有料プランは80,000円/月~ |
・無料プランなし
・有料プランは59,800円/月~ |
・無料プランなし
・有料プランは28,600円/月~ |
| 公式サイト |
「ナレカン」の詳細はこちら |
「Stock」の詳細はこちら |
「iTutor」の詳細はこちら |
「Dojo」の詳細はこちら |
「TeんDo」の詳細はこちら |
「Teachme Biz」の詳細はこちら |
「COCOMITE」の詳細はこちら |
活用されない社内マニュアル管理を定着化させるためにも、あらかじめツールの特徴・注意点を把握して、自社に最適なツールを導入しましょう。
マニュアル管理・共有ツールの比較ポイント
ここでは、マニュアル管理ツールの3つの比較ポイントについて解説します。自社に最適なツールを選ぶためにも、以下のポイントを意識して検討しましょう。
(1)作成の手間を省く機能はあるか
1つ目は、作成の手間を省く機能の有無です。
たとえば、作成したいマニュアルのテンプレートや基本フォーマットがあると、項目に従って入力するだけでマニュアルを作成できます。また、テンプレートを使えば「どこに何が書かれているか」が明確なため、内容を更新する際も短時間で修正できるのです。
このように、資料作成の手間が省ける機能が備わっていれば、従業員は少ない負担でマニュアルを管理できるようになります。
(2)マニュアルを定着化させる機能はあるか
2つ目の比較ポイントは、マニュアルの活用を促す機能の有無です。
マニュアルは作成して終わりではなく、関係者全体に定着化させる必要があります。そのため、マニュアルの作成だけでなく共有もスムーズにできる機能がなければなりません。
また、ツールの操作が複雑な場合、ITに不慣れな従業員が活用できず、社内に定着しない恐れがあります。そこで、誰でも簡単に操作可能な「ナレカン」などの使いやすいツールを選び、全従業員がストレスなくマニュアルを閲覧できる環境をつくりましょう。
(3)マルチデバイスに対応しているか
3つ目の比較ポイントは、マルチデバイスに対応しているかです。
業務時に少し確認したいとき、わざわざパソコンがある場所まで移動して起動するのは面倒です。とくに、現場作業をしている方はパソコンやタブレットを持ち歩くわけにもいかないため、スマートフォンでの操作が必須となります。
よって、マニュアル管理ツールを選ぶときには、場所の制約を問わずに気軽に使用できるマルチデバイス対応のものにしましょう。
ツールでマニュアル運用をするメリット4選
ここでは、マニュアルの適切な運用で得られる4つのメリットを紹介します。マニュアル管理が煩雑な場合は、早急にツール・アプリを導入しましょう。
(1)すぐに情報伝達できる
まずは、マニュアル管理ツールで業務マニュアルを作成すると、情報共有がスムーズになります。
たとえば、従業員へ業務を伝えるとき、紙のマニュアルでは印刷や配布に時間がかかってしまいます。しかし、ツールを活用すればマニュアルを印刷・配布するプロセスを解消できるため、情報伝達のスピード向上につながるのです。
このように、マニュアル管理ツールであれば速やかに情報を伝えられるので、資料共有におけるストレスを軽減できます。
(2)対応スピードが上がる
次に、必要な情報を見つけやすいため、対応スピードが上がる点も適切なマニュアル管理のメリットです。
たとえば、作業に関する”よくある質問”やFAQなどもマニュアルに記載しておけば、トラブルがあったときでも、担当者からの返信を待たずに対応できます。結果として「対処が遅れ、さらなる問題が発生する」事態を防げるのです。
また、ツールの検索機能を利用すれば必要なマニュアルをすぐに見つけられます。このように、マニュアルの適切な管理によって、情報へのアクセスがスピーディーになり、トラブルも迅速に対応できることが分かります。
(3)業務を見える化できる
さらに、マニュアルを適切に管理すれば、業務内容を視覚化できるメリットがあります。
紙媒体のマニュアルの場合は、作成者ごとに内容やクオリティのばらつきが発生しやすかったり、画像などの視覚的な工夫もしづらかったりします。そのため、従業員にとって「使いづらいマニュアル」になってしまうのです。
しかし、マニュアル管理ツールであればテンプレートを利用できるので、マニュアルの様式や品質にばらつきが出るのを防げるだけでなく、画像の差し込みも簡単です。その結果、業務内容も把握しやすくなり、内容の解釈に齟齬が生じる心配がありません。
(4)会社の損失を最小限にできる
最後に、適切なマニュアル管理ができれば、会社の損失を最小限にできることが挙げられます。
「責任者が急遽変わった」「商品の発注ミスが生じた」などの状況でも、トラブルシューティングのような社内マニュアルを適切に管理していれば”何をすべきか”がすぐに分かるため、スピーディーに対応できるのです。
また、マニュアルから「業務フローのどの箇所に問題があったか」の判断ができるので、再発防止にもつながります。このように、適切なマニュアル管理をすれば、有事に正しく対処でき、ミスや損失を抑えられるのです。
*トラブルシューティング=トラブル発生時に原因を探して取り除くこと
活用されないマニュアルを社内に定着化する管理ツールまとめ
これまで、活用されないマニュアルを定着化できるツール7選から、比較ポイントまでをご紹介しました。
マニュアル管理ツールを使うと、活用されなかったマニュアルの運用を円滑にしたり、トラブルも迅速に対処したりできるメリットがあります。また、マニュアルを簡単に作成できて、共有にも手間がかからないツールであれば、社内で重宝されます。
ただし、多機能なツールでは現場のメンバーが上手く使いこなせず、活用されない恐れがあるので注意しましょう。したがって、ツールを継続的に運用するには「ITリテラシーを問わずに使えるシンプルなツール」が必須です。
結論、メールを使える方であればすぐに使いこなせるほどシンプルな「ナレカン」一択です。
ぜひ「ナレカン」を利用し、マニュアル管理のストレスを解消しましょう。